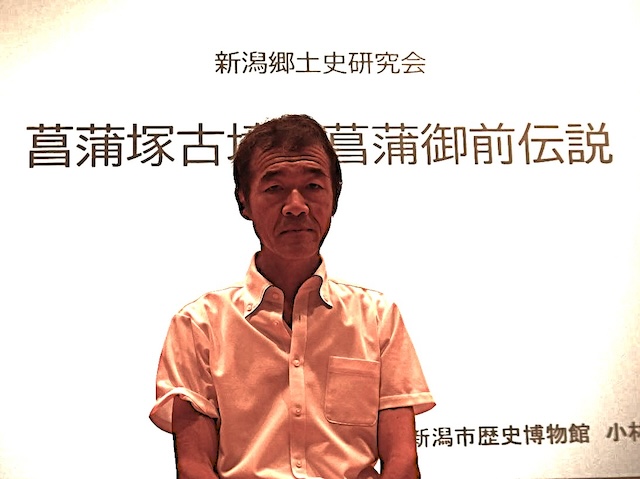9月の例会=報告
9月例会
令和6年9月15日(日)
演題:菖蒲塚古墳と菖蒲御前伝説
講師:新潟市歴史博物館副館長 小林隆幸 氏
〈講演要旨〉
菖蒲塚古墳は県内最大の前方後円墳で、4世紀に蒲原平野に君臨した有力者の墓です。古墳はやがて放置されますが、その異様性・神秘性から信仰の対象ともなり、古墳名称の由来となる菖蒲御前伝説との結びつきもあり、今日に至る人々との関係を概観してみます。
菖蒲塚古墳は4世紀半ば頃造られた全長53mの前方後円墳、金仙寺裏山の墓地の中に所在。副葬品には鼉龍鏡(径23.7㎝)・ヒスイ製勾玉や管玉があった。陪塚は隼人塚古墳。菖蒲塚古墳は大王墓の渋谷向山古墳(景行天皇陵)の5分の1で同企画。近接する南赤坂遺跡には北方系文化の系譜をもつ続縄文土器や土器も見つかり、菖蒲塚古墳の主のもとで北方の人々との鉄器の素材や皮などとの交易が行われていた可能性がある。
中世に入ると末法思想を背景に古墳が経塚として利用され、神聖な場所に位置づけられる。菖蒲塚古墳には、嘉応2(1170)年銘と享禄3(1530)年銘の経塚が出土している。嘉応2年銘は金仙寺が江戸期に発掘したもの、宋代の青白磁の小壷と合子、和鏡5点、陶製壺2点を埋納。享禄3年銘は六十六部聖が全国を巡礼し法華経一部を納めたもので越後では霊場として菖蒲塚が選定されたものと思われる。
菖蒲塚はその名称となった菖蒲御前の墓と伝えられている。金仙寺の山号は菖蒲山である。菖蒲御前は治承4(1180)年に宇治で戦死した源頼政の妻で、夫戦死した後に越後に逃れた。その子が後に小国氏の支城であった天神山城主となった。この菖蒲御前と関連するのが、金仙寺所蔵の聖観音坐像の底板に元徳3(1331)年「大施主貞阿」「女大施主」とある。また菖蒲塚古墳の近辺から掘り出された石塔に「菖蒲貞阿禅尼」印刻されている。過去帳には「菖蒲貞阿禅尼」が貞応2(1223)年没とあり、印刻名と同一人物と思われる。金仙寺で発掘された装身具も高貴な女性を連想させ、菖蒲御前伝説を後押しした可能性もある。
また古墳は盗掘され、鏡(鼉龍鏡)などが出土したとされ、盗掘品は市場に出ている。金仙寺の発掘の時期は文政期と思われるが、新発田藩の丹羽伯弘は鏡を実見し天保15年に拓本を取っており、この拓本は近年みなとぴあに寄贈されている。盗掘された鏡はしばらく最初の所有者が保管、昭和27年齋藤秀平が漢式の四神四獣鏡と判定し話題となった。同年上原甲子郎氏が東京国立博物館に持ち込まれていた鏡の拓本を取った。以降、鏡は所有者の手を離れ行方不明となり昭和36年に所在が分かり、上原甲子郎氏が購入、令和2年に東京国立博物館に寄贈された。昭和37年に鏡は新潟県指定文化財、金仙寺所蔵の経塚出土品(重要文化財)はみなとぴあで保管・管理、地域の重要な文化資源となっている。
菖蒲塚古墳は地域の首長の墓として造営、中世には神聖な場所として経塚の役目をもち、近世には伝説と結びついて信仰の対象となっている。古墳時代の遺跡だけではなく、各時代に役目をもった複合遺跡といえるのではないか。