7月の例会=報告
7月例会
令和7年7月13日(日)
「戦場の町と村 新潟市と戊辰戦争―新収蔵山口家資料を中心に―」
新潟市歴史博物館学芸員 田嶋悠佑 氏
<講演要旨>
令和3年春に山口家資料寄贈の打診があり、実物資料も併せて受け入れる条件で当館への寄贈となった。このことが本企画展のきっかけとなった。
山口家は蒲原郡山口新田(西蒲区)を開墾したと伝えられ、代々庄屋を務めた。今回取り上げるのは幕末・明治期に生きた山口謹一郎(1841~1890)に関する資料である。
慶応4年(1868)1月3日に鳥羽・伏見の戦いが勃発し戊辰戦争が始まる。戦争開始により会津藩が討伐対象とされる一方、幕府が越後の水原代官所所轄領を会津藩に引き渡したため会津藩の越後進駐が行われ、5月には米沢藩の越後への展開も始まる。6月1日には新潟町の施政権が米沢藩総督色部長門に委譲され、米沢藩を実質的な核として列藩同盟が新潟町を管理することになった。色部長門の日記によると、慶応4年6月10日の条に「山口謹一郎召し出す」とあり、両者の関係が初めて見える。6月28日には岩船郡下関に謹一郎が派遣されている。色部長門の家臣石山源内の記録にも謹一郎の動向がみえる。7月9日には光林寺(色部の駐屯所)に謹一郎が来て酒をふるまわれている。7月25日には太夫浜に新政府軍が上陸したため、謹一郎ら3人が物見に派遣されている。
次に山口家資料にみえる状況を示す。7月19日の覚には「謹一郎を兵隊隊長に任じ、士分とする。勝利後に禄知を与える」と記されている。7月の宛行状には「国替以来山口新田を開発し、庄屋を務め、米沢藩の動員に応じたことを賞し、三人扶持を与える」としている。同じく7月の朱印状では忠節を賞し、禄知を与えることを約している。8月の願書は山口新田の百姓41名が新政府民政役所に謹一郎の助命を嘆願したもの。8月4日の長州藩福原又市の書状には謹一郎が福原に会い酒を酌み交わしたこと、恭順し武器を渡す約束をしたことが記されている。8月11日の覚は福原の使者藤宮三九郎が謹一郎から渡されたゲベール銃50挺・刀9本の受取状である。旧式のゲベール銃ということからもわかるように、米沢藩があまり性能のよくない武器を支給していたことがうかがえる。
戦争を通しての謹一郎の位置づけを次に示す。謹一郎は幕末の政情不安を受けて政治運動への参加を志し、戊辰戦争の勃発を受けて米沢藩に属し、従軍した。しかし、米沢藩は謹一郎を取り立てるも武士とは一線を画した扱いをする。現実を知った謹一郎は早々に降伏し、以後は庄屋としての技量を生かす形で明治の世を生きていく。
山口家資料は戊辰戦争に参じた人々がどのような人生や背景を持っていたかをより詳しく明らかにしてくれる。資料所蔵者とのコミュニケーションや地道な資料整理作業がよい成果を生む。博物館のそうした仕事にも注目していただければありがたい。
〈この後、展示解説が行われた。〉

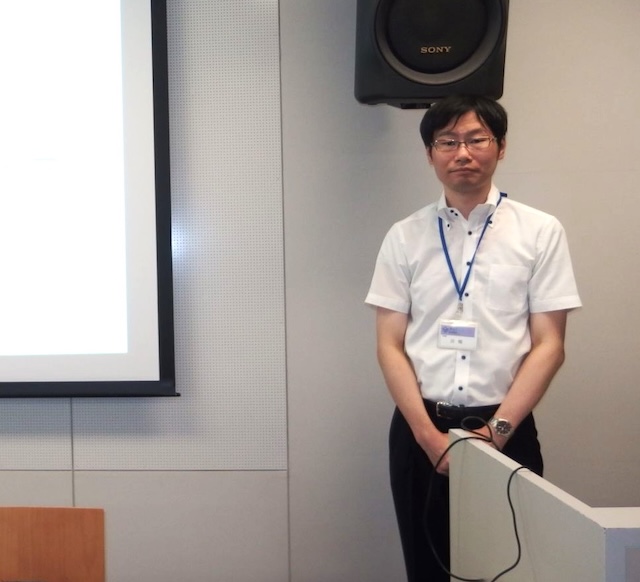
コメントフィード