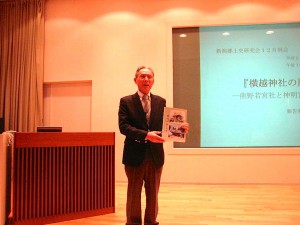8月例会
平成27年8月2日(土)
「古墳ワールド!―蒲原の古墳―」展を観る
新潟市歴史博物館学芸課長 小林隆幸氏
今回の企画展は、親子連れで来てもらいたいということから、蒲原の古墳をわかりやすく紹介する意図でタイトルをつけた。蒲原の古墳をまとめて紹介するのは今回が初めての企画である。
牡丹山諏訪神社古墳の発見に当館が深く関わっている。当館に寄贈された金塚友之亟氏採集資料の中から円筒埴輪の破片が発見されたことが発端である。古墳は牡丹山砂丘上に存在しているが、古墳を造ったムラは発見されていない。近くの山木戸遺跡から古墳時代の土器(4世紀)が出土している。県内ではほかに魚野川流域の飯綱山10号墳から壷形埴輪が出土している。発掘調査で出土した須恵器の器台破片は5世紀前半くらいのもので、須恵器としては新潟県で最も古く、大阪の陶邑で作られたものが持ち込まれた。阿賀野川河口の要衝部に存在、川砂が出土していることから一時期河であったところが陸地化し古墳が造られたと考えられる。
蒲原平野の古墳の多くは前期4世紀代の古墳であり、特に角田・弥彦山の東麓にまとまっている。稲葉塚古墳は蒲原で最初の古墳。山谷古墳は全長37メートルで県内最大の前方後方墳。菖蒲塚古墳からはダ龍鏡が出土、県内最大の鏡である。観音山古墳は丘陵上に作られた円墳で、葺石を持つ。同じく葺石を持つ緒立八幡宮古墳(旧黒埼町)は信濃川の河口近くの砂丘上につくられた。
阿賀野川を越えた胎内市の城の山古墳からは靫(ゆき)をはじめ多くの副葬品が出土した(県内最大の前方後円墳とされていたが、最近の調査で円墳と判明)。新津丘陵の古津八幡山古墳は県内最大級の円墳。
後期になると浦田山古墳(村上)、保内三王山古墳群(三条)、大萱場古墳(長岡)が造られる。浦田山古墳は竪穴系横口式石室を持つ。かつて磐船柵の一部と考えられていた。保内三王山古墳群は4世紀に造られた後、空白期時期があり6世紀に再び造られる。ここでは古墳のすべての基本形がみられる。大萱場古墳は朝鮮半島から伝えられた火葬の風習をとり入れた横穴式木芯礫室を持つ。
また、続縄文土器を使った人々が暮らしていた痕跡があり(南赤坂・御井戸B)、北方とのつながりを示している。
新潟県の古墳を概観すると、まず4世紀に蒲原に古墳が造られる。その後5世紀後半までは古墳は全く見られない。5世紀は雄略天皇の時代で、蒲原との関係は希薄になる。5世紀後半になると魚沼で古墳が造られる。6世紀から7世紀になると頸城に古墳が造られる。宮口・水科は7世紀のもので100基ある。越後の古墳は集中域が移動するという特徴をもつ。畿内の古墳と比較して大きさはとうてい及ばないが、それぞれ個性をもつ古墳である。
(この後、講師の小林隆幸氏の案内・解説で企画展を観覧した。)


2015年10月11日 9:26 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
7月例会
平成27年7月19日
「新潟花火の歴史とこれから-花火マニアの視点から」
横木 剛 氏(新潟市旧齋藤家別邸副館長・本会会員)
【講演要旨】
新潟市の花火の歴史、花火の鑑賞、花火のもつ価値、これからの新潟花火のあり方について、マニアの視点からみた提言を含めた講演であった。
まず花火の起源は、わが国では徳川家康が慶長18(1613)年に鑑賞した張り子の玉を打ち上げる手筒花火、新潟では江戸期に寄居村諏訪神社祭礼の仕掛け花火、古道の地蔵様縁日での打上げ花火といわれている。
かつて新潟花火は「川開き」(8月22・23日)と一体のものであった。その初見は従来の明治21年(旧版新潟市史)ではなく、明治16年に信濃川中洲で打ち上げられたもの(新潟新聞記事)との説明があった。途絶後、明治42年に川開きが復活、翌年に住吉祭も復活して川開き協議会が結成されたこともあって、昭和12年まで続いた。背景には、財界・新聞社・花柳界・商店・花火師らの協賛、打上げを支える土台が確立したことがあった。
一方で花火師も研鑽を積み、各地の研修会・花火大会への参加や色の多彩化や大玉化への挑戦の努力が継続された。
戦前新潟花火が日本一といわれた理由に、信濃川の川幅、財界・花柳界の支援、先進地からの技術導入や競技会による技術向上などがあったという。
新潟花火の地位が揺らいでいる現在、「花火は新たな価値を生む文化資本」の視点が必要であると提言する。市民の誇り、街の花火としての伝統の創造、総合的なプロデューサーの起用、密度の濃い構成、協賛金確保の経済的支援などが必要であると結んだ。新潟花火への熱い思い入れと辛口の時評も溢れた講演であった。
また講演終了後、新潟町の古い絵葉書の映像で街並みを語る時間がもたれた。フリートーキングのため会場が一体となり、郷愁にふけると共に歴史資料としての絵葉書を再認識した時間であった。

2015年7月24日 6:49 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
5月例会
平成27年5月16日
「吉田松陰、越佐をゆく―45日の滞在とその後―」
新潟県立文書館主任文書研究員 加納直恵 氏
〈講演要旨〉
吉田松陰が新潟を通った時の『東北遊日記』が残されている。写本ではあるが和綴の日記を新潟県立文書館で見ることができる。その日記をたどってみたい。
吉田松陰は文政13(1830)年長州藩士の子として生まれ、5歳で叔父の山鹿流兵学師範吉田大助の養子となった。嘉永3(1850)年21歳の時に九州遊学、同4年江戸に遊学、佐久間象山に師事し海防の必要性を強く意識する。相模、安房を調査し、次は北方ということで同4年12月14日東北への旅に出た。
江戸を出発した彼は水戸で約1か月間滞在、おそらく尊王攘夷について討論していたのであろう。会津には7日間滞在し藩校を見学、会津藩士と励まし合っている。2月7日新潟に入った。会津から新潟へは雪が深く歩きにくかったようであるが天気は良かった。兎を見てその色が白いのにびっくりしている。新潟では日野三九郎、中川立庵を訪ね、商人味方関右衛門らと日和山に登っている。
新潟から松前まで船で直接行こうとしたが、彼岸の日まで出帆しないとのことで佐渡行きを決意、2月13日出雲崎へと向かった。岩室、弥彦、寺泊を通り15日出雲崎に到着、海が荒れて渡海はできず13日間出雲崎に滞在。その間『北越雪譜』など多くの書物を読んでいる。2月28日ようやく小木に到着、真野に行き順徳天皇陵に立ち寄り尊王の心を昂ぶらせた。相川金山や黒木御所、春日崎砲台などを見て両津、小木、出雲崎を経て閏2月11日再び新潟に到着、日野三九郎、中川立庵を訪ね宿泊、味方関右衛門に詩を贈っている。
その後彼は秋田、弘前、盛岡、仙台、米沢、会津、日光を通り4月5日江戸に帰着した。東北の旅を終えた彼は「旅をしてはじめて広く深く学ぶことができた」と友人斎藤新太郎への手紙に記している。そしてその体験が国史への開眼、日本の航海術の未熟さや社会の後れへの認識、欧米諸国への関心などと結び付き、結果として彼のアメリカ密航計画、松下村塾主宰への熱意、安政の大獄連坐へとつながっていったのではないかと考えられる。東北の旅後の彼の生活には勢いがあり、同時にブレることがほとんどなくなったように感じられる。
旅の途中の越後、佐渡での経験が、松陰の人生の中で特に重要な位置を占めているのではなかろうか。

2015年5月28日 6:25 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
平成27年度総会
平成27年4月18日
菅瀬亮司副会長を議長に選出し、議事が進められました。
平成26年度事業報告・収支決算報告および平成27年度事業計画案・収支予算案を審議し、承認されました。
役員改選では、伊藤善允現会長が引き続き会長に選出されました。
平成27年度役員は以下のとおりです。
名誉会長 篠田昭[新潟市長]
名誉会員 蒲原宏[元がんセンター新潟病院副院長]
顧問 中村義隆[前会長]
相談役 和田右苗[前副会長]・小熊英雄[前副会長]・小川千代[前監事]
会長 伊藤善允
副会長 菅瀬亮司
事務局長 高橋邦比古
監事 齋藤義明・笹川玲子
理事 青木道・伊藤雅一・岡村澄子・毛島宏・桜井ミツ・佐藤千重子・関本昌隆・山上卓夫・横木剛・渡辺等
2015年4月29日 11:46 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
4月例会
平成27年4月18日
「碑(いしぶみ、モニュメント)に見る時代の形」
元新潟県立文書館副館長 本井晴信氏
〈講演要旨〉
標記の演題で、ひとりで自由に楽しめる後押しの一つとなるように、目に入った形や読めた文字と共にその背景に興味がわいたら調べてみよう、ということを趣旨としての講演であった。
まず「本井家」の墓を対象に話が展開された。本井家の代々墓は商売繁盛もあって天保10年に高さ約6尺弱の大きなものに改装された。遡る天保2年に幕府は、近年百姓・町人が身分不相応な墓を建てているから、髙さは4尺以下とすべしと触を出した。明らかに法令違反である。しかし伝承によると基壇の部分を土で埋め、高さを4尺以下に確保し、昭和初期に土をどけ全体を表出させたという。何とも庶民の知恵である。また、この墓のとなりに本井家4代目の背の低い墓1基がある。4代目は明治8年4月に亡くなったという。明治政府は明治6年7月に火葬禁止の布告を出し、同8年5月にこの布告を廃止した。つまり4代目は火葬にできなく、土葬で埋葬されたため、別の墓を造り、墓が二つならぶという状況となった。身近なところに歴史を見る所産が存在している興味深い話である。
それ以外に碑の事例として、個人の戦死者を悼み集落で合同葬儀をして位牌の形の19基の墓碑が並ぶ海老ヶ瀬諏訪神社境内、退役したり郷土が生んだ陸軍大将や乃木希典の揮毫による大型の「忠魂碑」が各地に見られ、越後では三条出身の鈴木壮六の揮毫したものが多いとの紹介があった。
モニュメントとしてかつて新潟駅前にあった二人の等身大の金子直裕作の裸婦像は、昭和34年の新潟駅の開業と合わせ東大通りの都市計画の完成記念として建てられたが、現在は近くの公園に移動して設置されている。県民会館前には新潟地震からの復興記念として昭和42年に現代工芸新潟会の複数の金工担当者が製作したフェニックスの鋳金があり、ほかにも高橋清作の親鸞の旅姿などの具体的な事例が背景とともに紹介された。
碑やモニュメントは、時代の様相を反映しているものの表れのひとつであることを再認識させられる講演であった。

2015年4月29日 11:40 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
2月例会
平成27年2月8日(日)
新潟市・沼垂町合併100周年記念展「沼垂」を見る
新潟市歴史博物館学芸課長 小林隆幸氏
〈講演要旨〉
「お蔵の松」はかつて沼垂小学校に植えられていた松で、周辺地域の一つのシンボルであった。そこは古くは新発田藩のお蔵があった場所である。
この沼垂は「渟足柵」として「日本書紀」大化3(647)年条にはじめて記された地名である。旧和島村八幡林遺跡から発掘された木簡に「沼垂城」とあり、沼垂が実在したことは確実である。越後国の成立や国府の所在地などとの関連からも注目され、また近年発掘された木簡や牡丹山諏訪神社古墳の発見など、沼垂周辺地域一帯のさらなる解明が期待されている。
中世史史料にも沼垂が登場している。たとえば永正15(1516)年伊達家文書の中に「のたりのわたしもり」が出てきており、「義経記」や京都醍醐寺の僧侶による「北国下り遣足帳」にも登場している。そして上杉景勝と新発田重家との対立の際にも沼垂が重要な拠点となっていた。
江戸時代は新発田藩の中心的な港として発展していったが、四度の移転があった。信濃川・阿賀野川の流れによる侵食の影響が大きかったと考えられるが、信濃川を挟んだ新潟町との訴訟が繰り返された。港の権益問題、中洲帰属問題、廻船入港問題等々、訴訟はほとんど沼垂側の敗訴で終わったが、沼垂町と新潟町の対立はながく続いた。
近代に入り、明治19(1886)年、萬代橋が完成した。萬代橋により沼垂と新潟が結ばれ鉄道の敷設も計画された。同30年北越鉄道沼垂駅が開設されたが、その開業前には鉄道爆破事件などもあった。同31年山の下と合併、大正3(1914)年に沼垂町と新潟市の合併が実現し、その後も信濃川右岸一体にかけて商業施設や工場群が建設され、また近代的港湾としても整備され、さらに大きな発展をみせていった。
このながい沼垂の歴史について、今回の企画展を観覧し、より一層理解を深めていただければありがたい。
(沼垂に関係した古い写真を映像で観賞し、その後企画展の会場に移動して「沼垂展」を観覧した。)


2015年3月11日 5:22 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
新春講演会・新年祝賀会
平成27年1月11日(日)
新潟会館において新春講演会並びに新年祝賀会が行われました。
新春講演会は、新潟大学教授橋本博文氏による「書き換えられた越後の古墳時代像―城の山古墳・牡丹山諏訪神社古墳の調査を通して―」と題する講演で、最新の発掘成果、研究成果が紹介され、あっという間の90分間でした。
100人を超える出席者があり、当初予定していた人数をオーバーし、急遽、机や椅子を補充する状況でした。牡丹山諏訪神社古墳をはじめとする越後の古墳時代、古代史について、興味関心を持っている人が多くいるのだと、あらためて感じました。
講演会終了後、恒例の新年祝賀会が行われました。当会名誉会長の篠田昭新潟市長の挨拶があり、乾杯の後、約2時間和気藹々、多くの人との交流を深めました。
〈講演要旨〉
越後において、古墳文化は従来上越を飛び越して下越の蒲原平野に到達したと考えられていた。しかし、妙高市観音平古墳群での前方後円墳の出現により、上越にまず古墳文化が到達したといえる。
また、胎内市城の山古墳の調査により、阿賀北地域での前方後円墳が確認され、下越にも古墳文化が早く波及していることが実証された。城の山古墳から漆製品、木棺、鏡、靫、勾玉、管玉等々が出土し、今後も調査・研究が積み重ねられていくことと思われる。
下越の前方後円墳として、西蒲区の菖蒲塚古墳が確認されているが、近くの南赤坂遺跡からは北方の続縄文土器が出土しており、北の集団と西の集団との交易が考えられる。宮城県栗原市入の沢遺跡においても、古墳文化を持っていた人々と続縄文文化を持っていた人々との交易、接触、戦いが想定され、今後注目される遺跡の一つとなっている。
古墳前期末から中期初頭に、新潟市秋葉区古津八幡山古墳が出現する。この古墳は越後最大の古墳であるが、円墳である。
今回調査された新潟市東区牡丹山諏訪神社古墳は、5世紀代の円墳ではないかと考えられる。出土した須恵器破片や円筒埴輪破片などから、近畿をはじめとした各地の勢力・技術とのかかわりが想定される。砂丘上に存在するこの古墳は、阿賀野川・信濃川の合流点であり、河川交通を掌握している有力者との関連が考えられる。近県各地の資料館には石棺の出土例やそれを復元した模型がいくつか展示・説明されている。牡丹山諏訪神社古墳にも石棺が入っていても「おかしくはないのでは」と思われる。そして、北関東や東北とのつながりについての研究も今後の課題であろう。
牡丹山諏訪神社古墳がつくられたあとは、今後の研究課題ではあるが、南魚沼市飯綱山古墳群の中期群集墳の台頭にみられるように、一つのクッションをおいて、南魚沼に政治的拠点が移っていったのではなかろうか。
牡丹山諏訪神社古墳をはじめ、今後も発掘・調査・研究を継続し深めていかなければならないと考えている。

橋本先生ご講演
講演会終了後、恒例の新年祝賀会が行われました。当会名誉会長の新潟市長篠田昭氏からご多忙の中ご出席いただき、激励のご挨拶をいただきました。

2015年 新年祝賀会

当会名誉会長 新潟市長 篠田昭氏
2015年1月23日 9:21 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
12月例会
平成26年12月20日(土)
「横越神社の風景―熊野若宮社と神明宮の合殿―」
本会会員・(財)北方文化博物館理事 神田勝郎氏
〈講演要旨〉
私の地元にある横越神社は熊野若宮社と神明宮とが合殿された神社である。今年の1月『横越神社の風景』と題し1冊の本をまとめることができた。
熊野若宮社は若一王子(にゃくいちおうじ)と呼ばれ横越下郷宮原に、神明宮は横越上郷にそれぞれ古く勧請された神社である。明治7年に熊野若宮社が神明宮の社地に移転し合殿を果たしていたが、大正8年の「奉遷宮村社 熊野若宮社・神明宮合殿御移転」の棟札も存在していた。
幸いに大正8年の棟札を立証する「合殿御移動」の時の古写真が五十嵐家に大切に保管されていた。その写真から、木臼を2段に重ね舟板を敷いて神殿(合殿)を載せ、木の丸太で50メートル引きずりながら移動したことが判明した。翌大正9年には横越下郷宮原にあった大鳥居も神殿移動に併せて搬送・再建された。この移設の時の古写真も幸運にも発見することができた。
横越下郷宮原の熊野若宮社の奥には、古くから「ジガ屋敷」と呼ばれた場所があり、かつては榎の大木があった。その地点はあたかも前方後円墳を思わせるような地形になっていた。また周辺には諏訪神社、千手海庵、行者塚、宗賢寺などがあり、一大宗教ゾーンのような感じのするところでもある。同時に明治5年頃の「家並図」を見ると、横越組大庄屋の建部家と小林家が並んで所在しており、横越下郷は要衝の地であったことがうかがえる。
横越神社の拝殿には安政5(1858)年の俳句奉納額や横越出身で群馬県知事を4期務めた神田坤六揮毫の扁額、さらに建部遯吾博士揮毫の大幟を写真撮影したものも掲額されている。そして昭和9年には境内地を囲む玉垣が築造され、神社としての見事な景観が整った。
このたび旧横越小学校の門柱を活用し、小林存の歌を彫字して歌碑として建立することができた。
ふるさとの堤乃茶屋の酒悲し
長橋渡るバスに手を振る
小林存さんらしい字であり、自分のふるさとを偲ばせる歌である。そして180名の浄財によって横越神社の社地の一隅に建立されたこの歌碑は今、横越神社の新風景となっている。
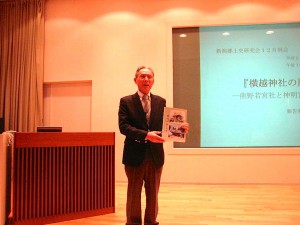
2015年1月4日 8:44 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
11月例会
平成26年11月15日(土)
「新潟湊に花ひらいた文化」
元新潟県立文書館副館長 小島正芳 氏
〈講演要旨〉
私は今までの良寛研究を通じて、出雲崎町の繁栄が良寛の活動を支えていた一つの要素であったと考えている。同様に越後の文化も越後の経済活動と密接に結びついていたと思われる。今日は経済的な活動を縦糸に、文化を横糸にして話をすすめていきたい。
二代目安藤広重の安政6(1859)年「越後新潟の景」がある。新潟の川や湊の美しさが出ているが、千石船や港の賑わいの様子なども描かれている。
元和2(1616)年堀直竒は新潟を湊として整備し、税を軽くする政策をとった。都市計画に対する先見の明があったといえる。その後、河村瑞賢によって西廻り航路が開かれ、新潟湊から多くの物資が大坂へ運ばれていった。なかでも蔵米が多く、それらは商人の手を経て各藩の収入源となった。「東講商人鑑」には廻船問屋の名前が記され、「越後土産初編」には各地の名物が記されている。
松尾芭蕉が新潟に来て泊まっている点も注目される。時代は元禄年間、新潟に俳諧の広がりがあり、新潟商人は商売のみならずさまざまな文化や教養を身につけていた。
新潟は絵画についてもすぐれた絵師を出している。その代表が五十嵐浚明である。江戸や京都で狩野派、土佐派を学び新潟に帰ってきたが、五十嵐元誠や五十嵐竹沙など一族もまた有能であった。そして片山北海、飴屋万蔵、岩田洲尾、玉木勝良、田辺忠蔵、白井華陽、石川侃斎、巻菱湖、館柳湾等々、多くの文人達が活躍した。
時代が明治となり、開港した新潟においても、従来からの商人に代わり新しい商人が台頭するところとなった。それに伴い、新潟の文芸も江戸時代からのものではなく違った路線をたどることとなった。明治期、新潟の商人の目は北海道へと向かった。畳表や藁などが北海道へ運ばれ、にしん、昆布などが新潟にもたらされた。
そして新潟の文芸も、太田木甫、日野資徳、山田花作など新しい担い手たちによって活躍の場が広げられていった。この3人に学んだ人物が会津八一である。会津八一の活躍は、いわば新潟の文化が東京で再び生かされるようになった、といえるのではなかろうか。

2014年12月15日 9:55 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
9月例会
平成26年9月21日(日)
「古地図が誘う越後の中世」
新潟県立文書館副館長 中川浩宣 氏
〈講演要旨〉
11世紀後半の越後の様子を描いた絵図として「康平図・寛治図」―いわゆる「越後古図」が有名である。この二つの絵図の特徴は、①新潟平野が海として描かれている、②佐渡に向かって幻の半島が描かれている、③複数の小島が描かれている、の三点であろう。
「越後古図」の評価をめぐっては様々な議論がなされている。その中で、近年、正確なものではないが地理的環境を読み取るある素材として使えるのではないのか、ハザードマップとしてとらえると「なるほど」と思える部分が存在しているのではないのか、海として描かれている越後平野は水没してしまう土地であるという意識で描かれているのではないのか、等々の意見が提示されている。
私は以前、横田切れ「水害図」の中の水に浸かった部分を見た時「越後古図」を思い出し、「水害図」と「越後古図」とがだぶって見えた。そして「越後古図」はハザードマップと同一ではないのか、評価に値する部分があるのではないのかと考えるに至った。
中世の越後全体を描いた絵図はなく、当時の状況を確認することはできないが、中世の越後平野は「水の平野」であったと考えられる。また気候変動の面から見ても「越後古図」が描かれたといわれている11世紀は暖かい気候のピークで、海進がすすんだ頃ではなかっただろうか。平野のかなりの部分まで水が入っていてもおかしくなかったのかもしれない。そのためであろうか、越後平野を根拠地にした中世の有力武士層はほとんど登場していない。頸城(くびき)と揚(あが)北(きた)には有力武将が多いのに比べ越後平野には有力武将は育たなかったように思われる。
越後平野は治水・排水事業の進展等により「水の平野」から「米の平野」へと変化していった。しかしその変化の過程でも洪水は頻繁に発生していたと想像される。中世においても、史料がなく不明な点は多いが洪水は繰り返し発生していたであろう。このような環境の中で、「越後古図」は越後平野のハザードマップとして、また「生産の土地」ではあるが水没してしまう地域であるということを想像させる絵図として描かれた可能性があるのではなかろうか。同時にこれだけの水害の土地を切り開いてきたということを後世の人々に示すため描かれたのかもしれない。
越後平野の一つの「履歴書」として「越後古図」をこれからも見ていきたい。

2014年9月29日 10:06 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
« 古い記事
新しい記事 »