10月の例会=報告
10月例会
令和6年10月20日(日)
演題:新潟開港と戊辰戦争-新潟奉行代理田中廉太郎光儀(れんたろうみつよし)の生涯と御料所新潟の終焉-
講師:東京大学史料編纂所学術支援専門職員 杉山 巖 氏
〈講演要旨〉
本日は新潟開港と幕末、明治維新期の新潟の歴史について、新潟奉行代理であった田中廉太郎光儀の生涯と関連させてお話したい。
新潟の開港が最終的に決まったのは慶応3(1867)年8である。その開港をひかえ外国方の上級事務を担当していた白石千別、糟屋義明が新潟奉行に就任した。また同4年正月、田中光儀が新潟奉行所ナンバー2の組頭として就任し、さらに同年閏4月新潟奉行勤向(奉行代理)に昇任した。
田中光儀は幕府代官所手代の子息として生まれ、のち浦賀奉行所の役人であった田中家の養嗣子となり家督を相続した人物である。彼は浦賀奉行所や長崎奉行所に在勤し、その後幕府の外国方の役人となり小笠原島問題を担当することとなった。この時小笠原島開拓担当の外国奉行組頭が白石千別で、その下の調役が田中であった。
また彼は横浜鎖港問題の交渉使節団の一員としてヨーロッパへ派遣された。使節団は文久4(1864)年正月上海に到着、その後各地を経由しパリに到着、フランスと交渉するが失敗、同年7月帰国。団員は失敗の咎を受け、田中も役職を離任した。
慶応3年10月14日に大政奉還が行われ、同年11月徳川家は新潟に在勤していた新潟奉行白石千別を江戸に呼び戻した。新潟開港が切迫していたため白石は江戸在勤の糟屋義明らと協議し、同3年12月7日の開港予定を翌4年3月9日に延期することを決定した。そして同4年正月新潟奉行所組頭に田中が就任し、白石、田中の二人は新潟に来た。二人は外国奉行所時代の上司と部下であった。
同4年3月15日明治新政府の北陸道鎮撫使が来越、新潟奉行も召喚された。鎮撫使にようやく会えた田中は行政事務の引き継ぎを命じられた。そして4月4日徳川家の指示を仰ぐため白石と田中は会津を経由して江戸へ行った。白石は新潟奉行を免じられ江戸にとどまることとなった。一方田中は奉行勤向に就任し5月2日新潟に戻った。戻った彼は新潟を米沢藩の「当分預所」とする決断を下した。この決断は徳川家の方針にそったもので田中が勝手にやったわけではないと言える。田中の行動はあくまでも徳川家の家来としての行動であった。そして6月2日田中は江戸に向かって新潟を出立した。
明治時代田中は豊岡県(現兵庫県)の県令に就任し、その一方で大木喬任や井上馨の顧問のような仕事もした。また木戸孝允との交流もあり新政府要人らに提言したりした。今その活動を物語る手紙などが残されている。

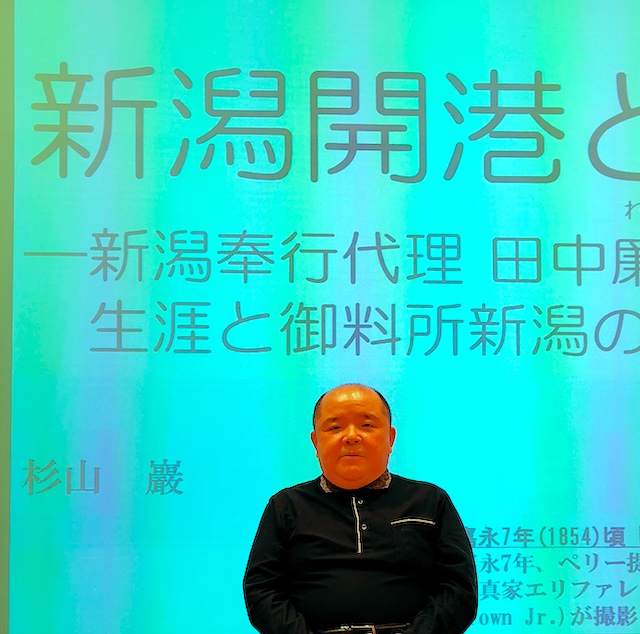
コメントフィード