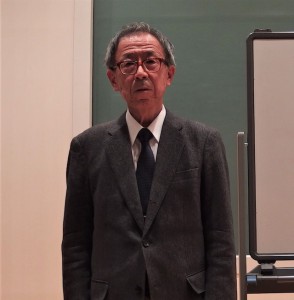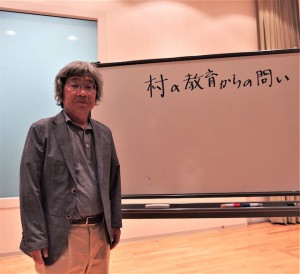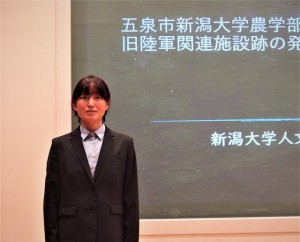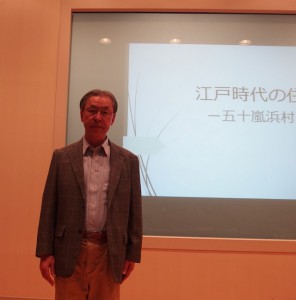11月例会
令和3年11月20日(土)
高野山清浄心院「越後過去名簿」に記されている「氏名」と「逆」について
新潟郷土史研究会会員 山上 卓夫 氏
<講演要旨>
真言宗空海(弘法大師)によって創建された日本の一大霊場高野山、その清浄心院(宿坊を経営)にある「越後過去名簿」より、上杉氏時代の越後とのつながりとその実態を探る。
当時の「高野僧」は「取次」(地方の寺院など)を拠点にしながら、地方を回って依頼を受けて供養料を得ることも多かった。「越後過去名簿」に残されているその記録の中には、大永8(1528)年に新潟新津屋四良衛門と同坂内新兵衛の身内の供養依頼が見える。また天文10(1541)年には、府中(直江津)の長尾為景(越後守護代)供養記録があり、為景死亡推定年が従来と異なる可能性も読み取ることができる。なお、その翌年には娘道五の供養依頼もあわせて記録されている。
そして、上杉氏-長尾氏のもとに連なる、色部氏、水原氏、新発田氏、安田氏といった国人領主層からの供養依頼、さらにその輩下の、例えば安田氏の田那部、高山、石塚、渡辺といった小領主(村殿)からの依頼記録も残っており、高野山とつながる越後における広域でのまとまりを窺うことができる。実際安田氏は、上杉家臣団の中でも相応の軍役を担う重臣として仕え、その輩下も「軍役衆」としてその中に組み込まれている。また「岩船衆」であった鈴木新右衛門や須貝藤左衛門が、生前供養である「逆」(逆修)を依頼していた記録が残っており、色部氏支配下地域においてもそのつながりが確認できる。
さらに、上田長尾氏の元々の拠点「樺沢」(旧塩沢町)に由縁のある、宮島氏、田中氏親族の供養が、天文4(1535)年に依頼された記録も残されている。この宮島氏らはのちに、上杉景勝によって取り立てられた家臣団である「上田衆」として、越後・佐渡全域に派遣されて支配力強化の一翼を担うことになる。文禄3(1594)年に、宮島氏(三河守)は栃尾から新発田へと、黒金氏(安芸守)は佐渡羽茂へと派遣されていることが、「定納員数目録」から確認される。
この「越後過去名簿」には合計1160件(含、年不明51件)が記され、うち生前供養「逆」の記載が223件(含、年不明2件)ある。他国の「供養帳」などと比してもこの「逆」の割合は決して高くなく、中世においては「擬死再生(よみがえり)」の儀式によって、幸福が来て寿命を長くするという信仰が広くあったものと考えられる。
こうした中で、僧侶へ依頼する供養だけではなく、「良(入)阿弥陀仏」などの号を刻んだ「板碑」を造立することも行われていた。しかしその際も、経済的な差異によって石に墨で書くだけ、又はただ石を置くだけという階層が大部分であったことを、郷土史を勉強する者として見通すことが大切である。
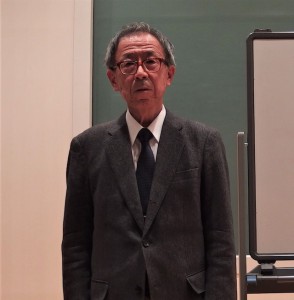
2021年11月27日 1:02 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
9月例会
令和3年9月19日(日)
「郷土のことばを考える 方言でココロ・カラダ・アタマを活性化」
当会会員 大田朋子 氏
<講演要旨>
「方言とは郷土の宝」と考え、郷土のことばを再発見しながらことばのもつ心理的・身体的な効用を考え、認知症の予防ができるかもしれない方言についてお話しする。
新潟県の概形を地図に表してみると日本列島に似ている。ことばの東西の分岐を考えるとフォッサマグナにあるのではないか。例えばお正月に食べる丸餅と角餅の分布をみるとフォッサマグナの東は角餅、西は丸餅。その餅を焼き餅にするのは東、煮餅にするのは西、但し新潟の海岸部と佐渡の一部は煮餅。直江津に群馬から嫁いだ女性が正月の餅の食べ方を姑に聞いたら「やかんでにらんだ」と答えた。嫁はヤカンで煮た、この誤解が嫁と姑を接近させたというエピソードが残っている。灯油ポリタンクの色は赤色の東、青色の西。昆布巻は関東の鰊、西日本の鮭の傾向がある。
ことばのアクセントについてもイス・クツ・ウサギなど東と西ではアクセントの違いがある。例えば「セナカ」のアクセントはセを強調、ナを強調、強調なし、の三つの形があるのは新潟県のみで、フォッサマグナの境にあることで東西の言語の複雑性もみられる。柳田国男は新潟県の複雑性にことばの調査を中断したといわれている。
方言を使うことで心や身体に効用がみられることがある。介護施設で体操をする際に動作の指示を新潟弁で話したら参加者の関心が強く、身体を動かすことに効果があった(該当ビデオとして新潟医療福祉大学作成のラジオ体操第一を視聴)。その先鞭は東北大地震後に東北弁で流したラジオ体操の有効実証があった。笑いはNK細胞にかかわり、方言を使った子供と高齢者の交流は互いの心を開き、場を和ませる効用があった。
「たくさんあること」表す方言には、いっぺ、いっぺこと、どっつり、ふっとつなど多々ある。2019年に本県で開催された第34回国民文化祭にいがたは、「文化のT字路~西と東が出会う新潟~」がテーマであったが、その大会に本県の歴史的背景と文化的多様性を念頭に置いた「ふっとつ」の方言が使用された。
高齢者のなかには、昔の記憶、ふるさとや郷土の話、ふるさとの方言、同級会の話などを何度でも繰り返す傾向もみられるが、話し手に同感、共感することが、本人の記憶を想起させ脳を活性化させるという。方言も一つの医療ツールの役割を果たしていることがある。方言の医療、福祉への活用を検討することなども今後考えていただきたい。アクセントもその地域の言い方を尊重し、方言は古くて恥ずかしいものではなく、人を活性化させるものでもあるという認識が大切なのではないか。皆さんから方言に関する情報をお寄せいただきたい。
(最後にラジオ体操のみんなの体操のビデオを見ながら、参加者は着座で身体をほぐす)

2021年9月21日 8:27 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
8月例会
令和3年8月21日(土)
村の教育からの問い~旧佐渡郡羽茂村全村教育~
前佐渡市立南佐渡中学校長 知本康悟 氏
<講演要旨>
かつては「村を育てる教育」が行われていたが、現在は「村を捨てる教育」となってしまっているのではないか。戦前は農業を中心とする第1次産業就業率が高く、それに対応した「村里の教育」が行われていた。「村里の教育」とは、家と村を担う一人前の良き村人を育てる教育であり、「地域(村)の子どもは地域(村)で育てる」という姿勢に基づいている。これに対し「学校教育」とは、近代国家の形成と工業化を担う人材(労働者・兵士)を育てる教育である。「学校教育」により得たものも多いが、なくしたものもある。学校教育と地域教育が一体となり「地域社会に、人間形成のための新しい共同の関係をどうつくるのか」が課題となる。そのヒントを、日本社会と地域と教育の転換期である1930年代から1950年代の羽茂村の地域と教育の歩みに探ってみたい。
この期間を3つに分けてみる。まず第1期は1930年から1945年であり、戦争の時代の「村おこし」の時期であった。この時期には、農山漁村経済更生運動の中で、柿の特産品化とともに村立羽茂農学校の設立という二本柱が立てられ、以後「柿づくりは人づくり」「村づくりは人づくり」という「村おこし」の考えが羽茂村の中に浸透していった。
第2期は1945年から1950年代前半であり、戦後羽茂村の地域文化運動の時期であった。1945年に歌人藤川忠治が東京から帰郷し、『歌と評論』が復刊された。これを起点に歌会から羽茂村文化会などの地域文化運動が生まれていく。翌1946年には酒川哲保が京都から帰郷し、羽茂村夏期大学が開催されるようになる。地域文化運動には戦地から帰った羽茂農学校の卒業生たちが集い、夏期大学には藤崎盛一や糸賀一雄、諸橋轍次、羽仁もと子、奥むめおをはじめ、一流の講師陣が集った。
第3期は1950年代半ばから1960年であり、羽茂村全村教育が行われた時期である。昭和29年に村内五か村が連合し、小中高一貫の教育を計画し、さらに幼児及び一般成人をも加えて全村教育をめざして出発した。教員育成のために村で立ち上げた内地留学制度、子どもを理解する手始めとしての精神衛生研究会の発足、村費教員の雇用など、先駆的な制度が進められた。こうした動きは母親の学びへと展開した。母の会が立ちあげられ、母の会読書会へ、さらに幼・小・中・高母の会研修会へと発展していった。これは地域に根ざした教育活動であり、30年間継続したのである。こうした「村つくりの教育」に指導的な役割を果たしたのが酒川哲保であり、村を育てる学びの共同体という彼の考え方は羽茂町長となった庵原健に継承され、その実践は民俗学者宮本常一に絶賛されるに至る。
以上とりあげた羽茂村の教育からの問いへの答えとして、「村つくりの教育」に学び、主体性をもった「村を育てる学力」を目指して取り組む必要があるのではないか。
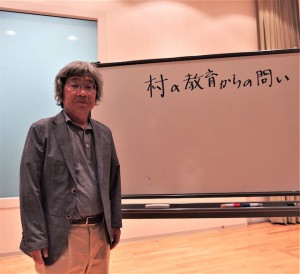
2021年8月24日 9:52 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
7月例会
令和3年7月17日(土)
「川・街・港 変わりゆく風景」展を観る
新潟市歴史博物館学芸員 藍野かおり 氏
<講演要旨>
今回の「川・街・港 変わりゆく風景」展は、アマチュアカメラマンの桜井進一氏による作品展であり、同時に信濃川を軸に、川・街・港がどのように変わってきたのかをテーマとした展覧会である。
現在の新潟駅が旧新潟駅(流作場)から移転したのは、白新線の計画とのかかわりが強い。白山駅と新発田駅を結ぶ白新線の計画は昭和14年からあったが、戦争中で中断、戦後の昭和31年開通をみるに至った。白新線の開通とともに新新潟駅の建設が同31年末に始まり、同33年4月29日に完工式が挙行された。新新潟駅は緑色の2階鉄筋コンクリート建て、ホームは4面、食堂など地階の名店デパートが開店した。駅前の東大通りの道幅は50m、緑地帯を設け周辺は耐火建築のみ許可、電柱を地下化し美化と防火対策を兼ね備えた街をめざした。同36年頃から帝石ビルやリッカーミシンビル、NHK新潟放送局が建ち始め、駅前の風景は大きく変貌していった。
万代周辺は新潟交通の関連施設が多く存在していたが、戦後のエネルギー不足を解消するため天然ガスの採掘が行われ、ガス井戸が25基もあった。しかし天然ガスの採掘を原因とする地盤沈下が顕著となり、同34年から規制が強化された。
万代周辺の変化を決定づけたのは同39年の新潟地震であった。新潟交通の各施設は壊滅的被害を受け、老朽化した施設の建て替えを余儀なくされた。同時に経営の多角化が検討され、同40年代新しい繁華街として万代シティが誕生、バスターミナル、ダイエー新潟店、万代シルバーホテルなどが建設され、万代周辺が新潟市の一大中心街になっていった。
戦時中、輸送力増強のため万代島に桟橋などが作られたが、戦争末期新潟港は機雷封鎖を受け機能不全に陥った。戦後の同27年ようやく安全宣言が出され、近海・北洋を含めた一大水産基地として万代島対岸に水産物揚場が建設された。それに伴い万代駅が貨物集約駅として完成し、また信濃川の土砂が溜らないよう導流堤が作られた。その後石油荷役の設備などもできたが、新潟地震の影響、そしてその復旧工事などで新潟港の景観は著しく変化した。同時に東港が造られ、関屋分水が完成し、新潟港の機能はより効率的な面から見直しがなされるようになっていった。
以上、新潟駅・万代周辺・新潟港についてその変化を紹介してみたが、展示室で写真を見ながら当時の状況を感じていただければありがたい。
(講演終了後、藍野かおり、桜井進一両氏による解説のもと、観覧を行った)
2021年7月26日 9:31 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
5月例会
令和3年5月15日(土)
五泉市新潟大学農学部村松ステーションにおける旧陸軍関連施設跡の発掘調査成果について
新潟大学人文学部助教 清水 香 氏
<講演要旨>
文化庁の調査では毎年9,000件の発掘がある。発掘することは遺跡を破壊することも意味するため、復元できる記録を残すことが肝要で将来的に分析できる様にしなければならない。今回は2019・2020年に新潟大学考古学研究室で実施した、新潟大学農学部村松ステーションにおける発掘調査で発見された戦争遺跡及び学生の取り組みについて紹介する。
五泉市の新潟大学農学部村松ステーションは明治30年以降、旧陸軍の村松練兵場及び射撃場として知られている。中村元氏は戦争遺跡としての性格を堀り下げ、旧軍施設と地域社会の関係を考察、地域貢献の上でも歴史的価値を確認することの重要性を指摘された(「新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター村松ステーションに残る旧陸軍施設関連資料の基礎的研究」『資料学研究』14、2017)。
これまで、村松ステーションにおいて本格的な踏査および発掘調査は実施されておらず、戦争遺跡としての位置づけを行う目的で発掘調査を行った。調査対象は塹壕跡と伝えられる堀・溝状遺構、同樹林内で確認された近現代遺物の集積、圃場にあったとされる軍用飛行場滑走路及び塹壕跡の確認である。
本遺跡は村松ステーション内に所在し、周辺には縄文時代後期末から晩期の遺跡が点在している。地層の基本層序は耕作土、黒褐色土層(黒ボク)、黄褐色土層(ローム)、黄褐色土と砂礫の混合土層である。樹林内の塹壕跡と伝えられる堀・溝状遺構から人為的な掘削の痕跡を確認、聞き取り内容とも一致することから塹壕跡と推測される。樹林中の遺物の集積は統制陶器(昭和15~21年)、歯磨き粉・化粧品などで昭和10~30年代とほぼ特定される。戦後の廃棄であり、医療廃棄物を含めはどこから運ばれたかという課題が残る。なお戦争に関する遺物は確認されていない。本県の秘匿飛行場(滑走路)には、西区旧山田島飛行場、南魚沼市の八色原飛行場などがあるが、村松飛行場は昭和20年6月にほぼ完成、約30町歩の広さがあり、重機を導入し学徒動員や勤労奉仕で造成された。圃場トレンチに軍用飛行場滑走路と考えられる痕跡を確認した。滑走路は塹壕を掘削して造成されたものと思われ、造成土と推測される黒色土層に挟まれる砂礫は近隣の河川から運ばれ、土を固め、落ち込みやぬかるみを防ぐ目的で利用された可能性がある。圃場には河原から砂利を運びまかれたものと思われる。
戦争遺跡の発掘は、地域社会に残る記憶を地域の資料と共に記録することで後世に伝えることができ、また戦争の痕跡を後世に遺し地域に還元する活動をとおして文化財への相互理解を深めることができる。今後は探知機による地層の分析、地形図や航空写真による比較検討も行う。本県における本格的な戦争遺跡の発掘調査が周知されることで、近現代遺跡の再評価につながることを期待したい。
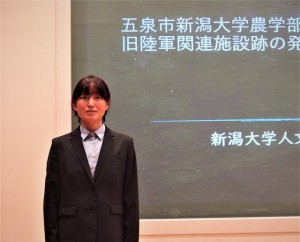
2021年5月17日 6:02 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
4月例会
令和3年4月17日(土)
戦国期の三ケ津を考える―蒲原津の盛衰と新潟町・沼垂町の成立前史―
新潟市歴史文化課学芸員・国立公文書館認証アーキビスト 長谷川 伸 氏
<講演要旨>
目下、蒲原津について関心を持っている。特に蒲原津と鳥屋野の関係である。本日は、中世の鳥屋野の位置づけ、蒲原津の地理的・歴史的位置と蒲原津の盛衰、近世新潟町・沼垂町の成立前提としての戦国期の交通路と三ケ津について、井上慶隆氏の「親鸞の鳥屋野布教についての覚書」(『郷土新潟』59・60号)を踏まえつつ述べてみたい。
まず、信濃側・阿賀野川と三ケ津について。中世特に戦国期に、信濃側・阿賀野川という大河川の河口地帯に、沼垂湊・蒲原津・新潟津という3つの湊(町)が古文書に表れるが、津と湊は別の概念である。津とは船と渡河点から考えた盛り場であり、湊とは水の流れと人や物が集まる場所のことである。中世以前から川と潟を使った内陸水面交通が発達し、川湊としての津が多かった。中世末期には、信濃川と阿賀野川の合流する河口部に三ケ津と呼ばれた港が発達する。天文20(1551)年には上杉謙信が三ケ津代官に蒲原津の大串氏を任命し、河口部の湊を一体的に管理した。新発田重家の乱後、直江兼続は新潟・沼垂を支配し、上杉の湊として拠点化、日本海交通の要として整備した。
次に、中世から戦国期の蒲原津について考えてみたい。井上慶隆氏は堀之内新田(中央区堀之内)を蒲原津比定地とし、鳥屋野を蒲原津の管轄下に含まれる公領とみているが、報告者もこの説にほぼ賛同の立場をとる。その上で、今一度鳥屋野と蒲原津について考察する。親鸞は承元元(1207)年2月に越後へ配流され、健保2(1214)年常陸国笠間郡稲田郷へ移住した。越後への配流期間は7年間であったが、この間の伝承が「親鸞七不思議」であり、鳥屋野の地名がみえる。鳥屋野という地名は京都郊外にある墓地の鳥辺野、すなわち境界・結界の場を想起させる。ここから、蒲原津の西の範囲は鳥屋野ではなかったかとも考えられる。
さて、戦国期の永正年間を境に蒲原津は衰退傾向となり、天文年間後半には「新潟・沼垂・蒲原」の三ケ津という取扱いに変わる。永禄期の「遣足帳」と比較すると、宿泊地は新潟であり、蒲原津は渡船場的になっている。新潟は永正年間の戦乱を通じて実権を握った長尾為景が新たな支配拠点として整備した湊町ではないか。蒲原津は新潟の登場により流通や徴税などの経済的な役割を奪い取られ衰退していった。
改めて鳥屋野に着目すると、鳥屋野は蒲原津(国津)から弥彦(越後一宮)に向かう北国街道のルート上にあり、親鸞関係遺跡寺院の存在する信濃川の渡河点ではないかと考えられる。なお、蒲原神社(青海神社)、神道寺、鳥屋野山王権現の比定及び湊の位置の解明などは今後の課題としたい。

2021年4月26日 8:16 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
3月例会
令和3年3月21日(日)
江戸時代の住民登録 ― 五十嵐浜村を例に ―
新潟郷土史研究会会員 本田 雄二 氏
<講演要旨>
新型コロナウィルス感染下の現在において、住民基本台帳に基づいて各自治体が様々な施策を行っているが、江戸時代においては、どのような形で住民登録がなされ、どのような役割を担っていたのか。五十嵐浜村に残る古文書を中心に、現在と比較しつつその実態を探る。
現在の住民登録は、出生、死亡、結婚、離婚、転居等に際し、その都度当該市町村の役所に届け出をして行われているが、江戸時代では、宗門人別改帳(戸籍・住民票を一冊にまとめたもの)に2~3月にまとめて記載・登録される形であった。キリスト教禁令下にあって、日蓮宗不受布施派を除く仏教徒が登録され、村に不利益を及ぼさない者としての身分証明的な役割を果たしていた。
江戸時代における正式な住民登録は、手続き上変更時点よりもやや遅れて実施され、結婚・離婚・移住等に伴う証文の発行も、宗門人別改帳面の書き換え時期に間に合うように、12月~正月にまとめて行われることが一般的であった。
全国一律の形式があったわけではないが、長岡藩領であった五十嵐浜村においても、移動に際しては、村で行う所請証文と寺毎で行う宗旨請(切)証文が、慣例に則ってやりとりされていたことが確認されている。また必要に応じて、村による身元保証や寺からの宗門保証の書状も作成されていた。そして最終的には、村役人から大庄屋を通じて領主へとまとめて提出される手筈となっていた。
こうした日常生活の中での変更とは別に、「不行跡者」や「欠落(出奔)者」が出た場合には「帳外」として、危難防止のために村から領主に願い出て、宗門人別改帳の登録から抹消された。長岡藩においては、幕府預り所を含めて「根限」として、他所へ欠落した場合には「根限証文」を、他所へ奉公に出る場合には5年間という期限をつけた「五ヶ年根限証文」の提出を義務づけていた。「根限者」はどこの宗門帳にも記載されず、村内居住は認められず、勝手にかくまうと有罪とされた。領主側としても、期限内に申し出がなかった場合には受け付けず、村役人の不注意として処罰する旨を規定しており、領内の治安維持に心がけていたことが窺われる。
なお、「根限」は「ねかぎり」と読むよりも、「「根元」「今現」と記される場合もあるところから、「こんげん」と読む方が自然ではないかと思っている。
このように、江戸時代における住民登録要件は、村による「慥成者」認定権である身元保証と、寺による「御法度宗門でない」認定権である宗旨保証であり、その有無が現在とは決定的に違っていたと言える。
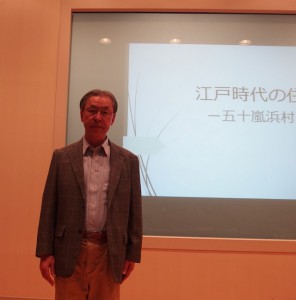
2021年3月31日 1:05 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
2月例会
令和3年2月20日(土)
「蘇民将来信仰」と「白山神社茅の輪神事・粽お守り」について
新潟郷土史研究会事務局長 高橋邦比古 氏
<講演要旨>
古代・中世は災害や飢餓、疫病などが日常的に発生していた時代であった。そのため人々は不可思議な力を持ったものにすがり、外部からやってくる悪魔や悪霊を遮断するため、お札や護符に信仰を寄せた。その代表的な例が「備後国風土記逸文」に由来する「蘇民将来」や「茅の輪」の信仰であろう。
「蘇民将来の子孫」と口で唱えたり、それを文字に記すことにより、また「茅の輪」を身につけたり、くぐったりすることにより魔除け、疫病除けに効果があると考え、その信仰は全国に広がった。
新潟市南区の馬場屋敷遺跡(旧白根市庄瀬)から「蘇民将来子孫」と記された中世期の木簡が出土している。別の木簡にも「蘇民将来子孫」の文字とともに梵字や呪文が記されており、中世の頃より新潟市周辺に蘇民将来信仰が広がっていたことがわかる。同様に阿賀野市の腰廻遺跡(旧笹神村)からも「蘇民将来」や「南無(无)牛頭天王」と記された木簡が出土しており、蘇民将来信仰とともに牛頭天王信仰も広がっていたことがわかる。
この牛頭天王は、もとはインドの祇園精舎の守護神で、のちに除疫神として京都の祇園社(八坂神社)などで祓われた神である。毎年行われている祇園祭はとくに有名で、悪疫を封じ込めるために行われたのが起源である。長刀鉾を先頭にした鉾9台・山14台の「山鉾巡行」は祇園祭のハイライトになっている。
蘇民将来信仰と同様に茅の輪くぐりも全国に広がっている信仰の一つである。新潟市中央区の白山神社では毎年6月晦日、「茅の輪くぐり」あるいは「夏越の祓い」とよんでいる神事を行っている。直径4m程の茅の輪を左回り、右回り、左回りと3回くぐる神事であるが、茅の輪をくぐれば気を祓い身を守るという信仰である。輪をくぐった参拝者には直径10㎝程の「茅の輪」が配布されている。
同神社には「粽お守り」も作られている。茅(チガヤ)は罪けがれを祓う力があるとされ、その茅を円錐状にして粽を作り、それをお守りとして玄関などに懸け災いを避けるという信仰である。
新潟市関屋地区をはじめ各地で白山神社門札や金刀比羅神社(宮)門札、善宝寺(山形県鶴岡市)お札などが貼られている家を見ることができる。今日のように近代的な科学万能の社会になっても、お札や護符に対する信仰は生き続けていくように思われる。

2021年3月6日 6:14 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
1月例会
令和3年1月16日(土)
演題 新潟県 県民性の歴史
新潟青陵大学特任教授 伊藤 充 氏
〈講演要旨〉
1 私が県民性の歴史を研究する理由
新潟県の県民性の歴史を見るときに興味深い全国統計結果がある。他の指標は決して上位ではないが、NHK受信料支払率2位、学校給食費支払者率3位と責任感の強さを表す。また、ある中学校で作成した「学習指導案」に生徒の実態として必ず書かれたキーワードが「まじめに取り組む」「素直に応ずる」「消極的」「表現力に乏しい」であり、先輩教師も後輩の若い教師も常套句としてきた。これはまさに現在の新潟県の県民性の一面であり、負の県民性である。これから世界の子供たちと共に生きる子供として成長していくためには、自らの県民性の歴史をしっかりと振り返る必要がある。そこで今日は新潟県の県民性を歴史・人物史・民俗史の観点から解き明かしたい。
2 県民性は、どのように生まれたか?
井上慶隆氏は、県民性の形成を雪の生活、水との闘い、真宗門徒の生活、郷村の学問と教育に求めている。これは横の広がりを重視する視点であるが、私は縦割りの視点をとり、県民性を政治史・社会史・産業史・民俗史などの時間の積み重なりから総合的にとらえたい。
今回は政治史から始める。結論的には新潟県の歴史は県外の人々により支配され続けたのが新潟県人であり、そこに県民性形成への根源が求められるだろう。縄文人の遺伝的形質を最も受け継ぐ新潟県域へ渡来系の遺伝的形質を持つ弥生人や古墳時代人が大和朝廷として支配をのばし、平安末期には、秋田に出自をもつ城氏が平氏政権の越後守に任命される。鎌倉期には滋賀の佐々木氏、静岡の北条氏、群馬の新田氏が守護を務め、南北朝期には栃木の上杉氏が守護、神奈川の長尾氏が守護代となった。近世になると秀吉により高田に岐阜の堀氏、新発田に愛知の溝口氏、村上に長野の村上氏を配置した。家康が江戸幕府を開くと、高田藩は六男忠輝改易後に群馬の酒井氏、兵庫の榊原氏など、長岡藩は愛知の牧野氏、新発田藩は溝口氏、村上藩は愛知の内藤氏、村松藩は堀氏というように武家政権の時代は、頼朝・秀吉・家康の家臣で関東・東海地方出身の支配者が多かった。明治以降になると歴代の県令・県知事は、京都の平松、佐賀の楠本・籠手田、鹿児島の永山・篠崎・千田と薩長土肥の維新政府の藩閥支配がつづき、新潟県出身の知事は、1947年の民選知事岡田正平をまたなければならない。このような状況で形成される県民性は、「実利的」「名より利益をとる」「消極的」などが指摘されることになる。
次に人物史をみるなかで特に新潟県の「清酒」ブランドの礎を築いた人々をみたい。江戸時代の越後の酒は、軟水を使うので「金魚酒」とよばれ、薄くてまずい酒の代表とされた。明治以降伏見・灘の芳醇な銘酒をめざし改良につとめた。速醸元の発明で革命を起こした江田鎌治郎は酒造業のために特許を申請しなかった。「酒博士」と呼ばれた坂口謹一郎は酒造史と全国の酒蔵の調査・研究をした。太平洋戦争期に政府は酒造の停止と統合を進め、石本酒造や宮尾酒造などは休業蔵となり、潜水艦の部品となる酒石酸を製造させられた。戦後酒不足に直面した政府は、模造酒である「三倍醸造清酒」の生産を奨励した。関東信越国税局鑑定官田中哲郎は「研醸会」という酒造研究会をつくり、酒蔵に技術指導をした。その弟子である石本省吾は「幻の酒越乃寒梅」を生み出した。さらに嶋悌司は「新潟清酒学校」を創立し、特に中小の酒蔵を育成し、銘酒「久保田」をつくりあげた。ここからは「粘り強い」「現場を大切にする」「忍耐強い」などの県民性が導き出される。
次に「県民性の再生産」という視点で、民俗史の「ことわざ」からみたい。第一の「越後の一つ残し」、消極性や雪国山村の旅人への優しさ、第二の「越後には杉の木と男の子は育たない」「亭主くわせられないば、嫁に行くな」、男子(特に長男)の凡庸性、女子のたくましさ・生活力、第三にの「頼まれれば越後から米つきに」、江戸の米つき行商人は、越後出身者が多く仕事はきついけれど、越後人の誠実さを表している。こうして新潟県民は、暮らし・習慣・労働慣行・雪の影響などを「ことわざ」として残し、自らの県民性を再生産しているのであろう。
最後に新潟県の子供たちが将来、世界に貢献し名誉ある地位を占めることを心から祈って、今日の講演とします。

2021年1月25日 1:07 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
12月例会
令和2年12月20日(日)
新潟県官員録出版ことはじめ
東京大学史料編纂所学術支援専門職員 杉山 巖 氏
<講演要旨>
江戸時代の幕府や朝廷の職員録は木版で刊行されているが、いわゆる「藩」の職員録はまず刊行されることはなく、明治時代になって地方版の職員録も刊行されるようになる。今回は新潟県の職員録が刊行され始めた経緯を探りたい。
慶応4(1868)年閏4月に政体書が発布され、府・藩・県の三治制となった。府は幕府の御料所(天朝御領=直轄領)のうち都市部、藩は大名の私領、県は天領のうち農村部を指す。
江戸幕府の職員録は「武鑑」、朝廷の職員録は「公家鑑」があり、幕府には2万人以上の職員がおり、ある程度の需要が見込まれたことが出版の要因となった。なかにはハンディ(小型)の武鑑や町人が年始代わりに配布した一枚刷りの武鑑もあった。町人が求める背景には、係争問題が発生した時の訴訟の窓口になる三奉行も記載されている事も関係した。地方の大名には手書き、書写したものが伝わっている。例外的には御料所の司法・行政を担当した代官や管轄の大きな郡代の職員録が「県令集覧」として出版されている。
明治政府の初期は頻繁に官職の制度や役職が変化した。明治元(1868)年には各種職員録が多数出版された。版元は京都の村上勘兵衛、武鑑を刊行していた出雲寺万次郎など。明治元年12月には『官員録』を村上勘兵衛・井上治兵衛が刊行。なかには官職制度が頻繁に変わるため製本に至らず反故になった職員録も多く、明治9年に出雲寺が刊行した教科書『初学地理書』は明治6年太政官正院の職員録を刷った紙を再利用して使われている。また書き込みのある反故紙が使用された例もある。
明治に入り新潟県の職員録で最も古いものは、明治4(1871)年正月の『新潟県職員録』である。新潟奉行所役人で新潟県官吏となった福原家に伝来するもので(現新潟市歴史博物館保管)、明治4年未正月に久須美喜内が刊行している。初刷りと後刷りがあり、明治3年と思われるものは「徒刑守久須美喜内」とあり、明治4年のものは「仲方久須美喜内」とある。久須美喜内は新潟奉行所の足軽であり、明治3年に徒刑守(刑務官)、4年には仲方(交易税業務)となっている。『公文録』には「当県官員掌中録、便利ノ為メ、別冊ノ通、徒刑場御彫刻為致候条、此段御届ニ及ヒ置候、以上、庚午十一月五日 新潟県 弁官御中」とある。則ち官員掌中録(小型版)を刑務所の労役を使用して木版彫刻させたので弁官に御届けします。庚午(明治3年)11月5日。と記録されている。明治3年に刑務所の監督者であった久須美喜内が、労役を使用して新潟県初の官員録(職員録)を出版・刊行したものが初めである。翌4年に改訂版刊行、以降県の官員録は数種出版され、明治7年には金属活字も出版された。

2020年12月23日 5:09 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
« 古い記事
新しい記事 »