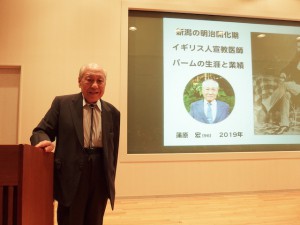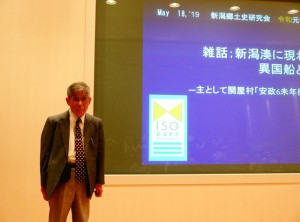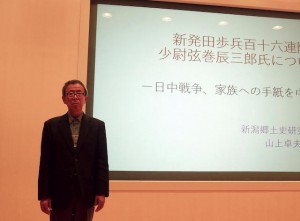11月例会
令和2年11月21日(土)
明治12年西蒲地方のコレラ騒動~伊藤家日記にみる農民生活~
新潟郷土史研究会理事 伊藤雅一 氏
<講演要旨>
現在、新型コロナ禍にあるが、関連して今から約140年前の西蒲地方のコレラ騒動について、主として伊藤家日記を題材に紹介してみたい。
前段として、感染症について、世界史的視野からみていくこととする。まず、感染症とは微生物(病原体)が人間や動物(宿主)体内に侵入・繁殖したためにおこる病気である。病原体とは感染症の原因となる微生物であり、ウィルスや細菌がある。
次に、歴史に名を残す感染症について、触れてみたい。まず、①天然痘について。痘瘡・疱瘡ともいわれ、致死率は高かったが、1796年に英医師ジェンナーが種痘を開発し、1980年にWHOが根絶を宣言した。②ペストについて。黒死病ともいわれ、1347~50年に西ヨーロッパ各地で大流行し、全人口の約三分の一が死亡した。農業人口の減少・賃金上昇により、農民の自立化が進行し、近代社会の移行が促進されたと言われている。③スペイン風邪について。第一次世界大戦中にヨーロッパ全土に感染が拡大し(世界人口の25~30%が感染、米大統領ウィルソンも感染)、終戦を早めることにつながった。
さて、本題の「伊藤家諸日記帳」にみる西蒲地方(福井村)の明治12年コレラ騒動をみていきたい。コレラは、「虎狼痢」・「虎狼狸」・「虎列拉」などとも表記されるが、汚染された水や魚介類を飲食することで感染し、糞便や吐瀉物の河川への排出で感染が拡大される。明治12年3月ころに西日本で発生したコレラが東日本へ感染拡大し、新潟県の衛生掛発表では10月に患者累計数が5,184人、死者累計数3,110人を数えた。新潟下町と沼垂町で暴動が発生したため、新潟県は8月に軍隊新発田分営に出兵要請をしつつ、魚介類・青果類の販売禁止を全面解禁し、暴動の原因解消に努めた(『新潟県史』通史編6)。
西蒲地方でも多くの感染者を出している。福井村の「伊藤家諸日記帳」には、7月23日の神明神社祭礼、8月27日の大般若経祈祷と、病魔退散の儀式執行がみえる。8月19日には村中集会が行われ、虎列痢規定が制定された。具体策として、他村者立入拒否のため立番を置き、村民死亡の香典を1銭とする申合せが行われている。まさに、ロックダウン、クラスター対策である。明治15年には、福井村コレラ予防組合が作られ、福井村伝染病予防御約束法が村の全戸の署名捺印で制定された。換気、薬剤散布、衣服、飲食、救済施設、葬送など細々とした内容で、現在の新型コロナ感染対策と似通ったものが多い。
最後に、我々人類は新型コロナの教訓をどう生かせばいいのか、付言したい。政治家は「公平・公正」に国民の生活を守ること。企業経営者は「利他」の心をもって蓄えた財力を社会の弱者のために提供すること。我々一人ひとりの市民は「隣人愛」の心をもって身近な人のために自分のできることをする、ということに尽きるのではないだろうか。

2020年11月24日 12:16 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
2月例会
令和2年2月15日(土)
廻船問屋「当銀屋」の成長と北前船
新潟郷土史研究会理事 横木 剛 氏
<講演要旨>
かつて廻船問屋齋藤喜十郎家・前田松太郎家について研究してきたが、本日はさかのぼって江戸期の当銀屋の具体的な経営にあたってみたい。
はじめに廻船問屋は三つの役割をもっている。諸国廻船と湊町の商人を仲介して取引口銭を得る。取引に課税される仲金を納める。船頭の世話と管理を行うという役割である。
本日のテーマの当銀屋は与板の備前屋の出店から始まる。備前屋は元禄期から米取引を行い、新潟湊からも出荷していた。さらに新潟に拠点を置くため、新潟商人の権利を取得し出店を開き当銀屋の屋号を使った。享保頃の米価の低落傾向や松ヶ崎掘割の影響のため廻船の新潟入津数が減少、衰退する廻船問屋も現れた。新潟出店も延享期に営業不振となり、出店で働いていた備前屋親戚の江口善蔵が引き継ぎ、宝暦6(1756)年に廃業した廻船問屋加賀屋津右衛門の株を取得して廻船問屋となった。株の取得とは得意先(顧客)の引き継ぎも意味した。また宝暦2年の成立から明和4(1767)年に町老、天明2(1782)年には検断となり町役人としても重きを成してくる。
現在当銀屋江口家文書(約1400点)は新潟市に寄贈されている。当銀屋の経営を示す嘉永3(1850)年の史料をみると、売口銭500両、買口銭1,000両である。口銭は取引高の1.5%のため、取引高は売3.3万両、買6.7万両となる。ほかに貸金利息などの費目も分かり、損益を合計してこの年の利益は1,100両となっている。
北前船は売買価格差によって経営を維持している。資金不足の場合は現金補填、借金もあるが、取引先の廻船問屋に資金を積んでおく場合もある。天明8(1788)年の店卸帳をみると6,000両の「粟崎差引預り」がある。これは顧客である加州粟崎の北前船主木谷藤右衛門からの預り金である。木谷家は遠隔地の材木の輸送販売から成長し諸藩の蔵米も扱った。寛政3(1791)年に当銀屋が木谷家に送った書簡には、新潟湊における木谷船積入れ、廻船の修繕、蔵米船の扱いが優先する慣行、能代鉛や三田米など商取引に関する情報を報告している。また天明6年の帳簿には、当銀屋が新潟湊のほかの廻船問屋への貸付金を記載している。
当銀屋は、日本海海運に買積船が増加してきた時期と呼応して成長している。北前船主は取引先湊の廻船問屋に対する預け金の仕組みを活用して経営を展開、当銀屋はそれらの資金を活用してほかの廻船問屋に貸付けを行い、それがあらたな廻船問屋からの経営資金として投下もされている。新潟町においてこのような多様な金融の動きが背景となって、盛んな商品流通と相俟って湊の繁栄に繋がっていった。

2020年2月20日 6:43 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
1月新春講演会
令和2年1月12日(日)
阿賀野川舟運と下条船
新潟大学人文学部教授 原 直史 氏
<講演要旨>
本日は阿賀野川の舟運について、中でも特別に活動した下条船についてお話したい。
江戸時代、幕府や藩は米で税を取っていた。そのため各地の年貢米を移動させなければならず、その移動には馬よりも船が使用された。船の方が大量に積むことができたためで、江戸時代は河川交通が活発であった。
越後平野において長岡船道や蒲原船道など、船道とよばれる特権的な組織がつくられた。そして船道は各河川における特定ルートを掌握していた。このような船道に対し下条船はやや異なる展開をみせていた。
阿賀野川は新潟と会津を結ぶ重要な河川である。その旧小川荘周辺は江戸時代会津藩領であり、津川町、海道組、鹿瀬組、上条組、下条組に地域区分されていた。阿賀野川の流れは津川・会津間が急流のため、船や馬からの荷物の積み替えで津川は交通の要地として栄えた。津川船道が存在し津川町、下条組の船持を統括していたが、津川町と下条組の船株数について文化15(1818)年の史料を見ると、津川町は大艜21、小艜3、下条組は大艜66、小艜28で下条組の方が多い。この船株数の違いなどから、下条組の船持の肝煎たちが独自の集団となり、次第に船道と同等の機能をはたしていった。
下条組五十島村渡部家文書の中に、天明7(1787)年から慶応2(1866)年までの舟運経営を伝える史料がある。「積荷勘定帳」や「金銭受払帳」などである。天明7年の史料には薪の仕入値段と売値が記され、薪の売買価格差により利益を得るという買積経営の様子が記録されている。さらに弘化2(1845)年の史料から、五十島を出た船が中の口川、刈谷田川、小阿賀野川など複数の河川にまたがり広く航行し、下条船の活動範囲は越後平野全体に広がっていたことがうかがえる。
この背景には六斎市の存在が大きい。渡部家には各地の市日を記録した史料が残されており、渡部家の船は六斎市を巡回しながら売買していたのであろう。そして大きな船が入ることのできない土地では、その土地で活動している小船と連携しながら経営を成り立たせ、大野、酒屋、満願寺など拠点となる停泊地では必要な情報を入手し、次の目的地への判断材料としていた。さらに大友村など在郷町とはいえない村でも、薪の売買を取り次ぐ商人が存在していたことも重要である。
このような下条船の活動は、地元の長岡船道や蒲原船道と競合しなかったのであろうか。会津藩のもとでの下条船の活動であり、他藩でもこのような例はあったのであろうか。今後の検討課題であると考えている。

2020年1月30日 1:47 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
12月例会
令和元年12月21日(土)
明治三年の危機・新潟通商司
国立歴史民俗博物館プロジェクト研究員 青柳正俊 氏
<講演要旨>
「新潟通商司」については、ほとんど知られていない。『新潟開港百年史』や『新潟県史』の記述も正確とはいえない。これは資料の不足によるものである。確かに、日本側の資料は少ないが、これまで知られていなかったイギリス外交文書を丹念に見ることで通商司の問題を正しくとらえることができる。本日は、イギリス外交文書を中心に読み解くことにより、実際に新潟で何が起こっていたかについて話したい。
明治2年12月に新潟通商司及び新潟商社が設置された。しかし、翌3年7月に新潟通商司は撤退するに及んだ。設置された期間はわずか七か月に過ぎない。この間の経緯をみていく。明治3年初め、新潟通商司及び新潟商社はこの地の商業秩序の改革に着手する。布告類を発し、「新たな商法」が始まった。これに対し、新潟港の動揺が顕在化する。地元商人らの嘆願にもかかわらず官員・商社が強圧的に施策を強行し、その結果、二度の商業活動の麻痺状態を含む少なくとも二か月以上の混乱が続くこととなった。
この間、外国領事から新潟県への抗議も誘発された。ただ、この時点までは事態は新潟での動きにとどまっていた。だが4月に入ると東京へと波及する。外国領事からの抗議の報告を受けた中央政府は「書面へ下ケ札」をしたため、布告類を改めるべきことを明示した。並行して、中央政府とイギリスとの度重なる談判が行われた。
談判後、イギリス領事は新潟での新たな商法が適宜に是正されたと認識した。しかし、新潟では通商司・商社が県布告を上書きする告知を掲げた(「商社門前の掲札」)。新潟ではなおも「新たな商法」が継続しているらしい、という報に接したイギリス公使パークスは外務省への事実確認に加えて書記官アダムズを急遽新潟に派遣した。こうして、不意打ちに近い談判が行われた。アダムズは3月の「触書・覚」の撤回を求め、県はこれに応じ「取消し布告」を発した。
しかし、県では中央政府からの適切な指示がないなかでアダムズからの叱責に晒されたことへの強い不満があった。アダムズの追及に対して弁解したが、政府は一切取り合わなかった。結果として新潟通商司は撤退を余儀なくされ、事態の幕引きが行われた。三条西県知事が更迭され、本野大参事の問責が行われた。ここで、本野大参事はどこまで知っていたのかが問題となる。パークスは本野の非を追及したが、本野はこれを否定し、明治政府は本野擁護に徹した。結局、本野問責は未決着に終わった。
いまだ解明すべき課題は多いが、交易活動の活発化が期待された開港2年目の矢先を襲った通商司政策は、以降の新潟港低迷を決定づける要因の一つではなかったか。

2019年12月31日 11:32 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
11月例会
令和元年11月16日(土)
青年民権家山添武治と5人の子供たち
新潟県立文書館嘱託員 横山 真一氏
〈講演要旨〉
明治期に自由民権運動と新聞事業に取り組んだ山添武治とその家族の“ファミリーヒストリー”をたどることによって、明治・大正・昭和の新潟県の歴史を考えてみたい。
1 山添武治―自由民権と新聞事業-
山添武治は、万延元(1860)年西蒲原郡金巻村に生まれ、明治13~20年代にかけて自由民権運動に参加。15年2月には東京から県下に檄文を発送し、「自由制度の確立、人民の権利定着、自治の元気培養、国の活発化、国家の安定、日本の五大陸への発展」を訴えたが、24年師と仰ぐ山際七司が死去すると、政治活動から退く。29年に庄内藩士黒崎与八郎の三女柱(ことじ)と結婚した。明治30年以降は、新聞経営に従事『新潟日報』『新潟中央新聞』『新潟毎日新聞』を発行し、新潟県の新聞事業発展に貢献した。
2 山添柱(ことじ)-キリスト教と子供の教育-
明治29年に17歳で36歳の武治と結婚し、不在勝ちの武治にかわり家を守り、36年にキリスト教に入信し、心の支えとするとともに、西洋の学問に関心を高め、庄内藩武士の家庭の教育熱心な気風から、子供たちの向学心と自立心を育んだ。「自慢・高慢、馬鹿の内」が柱の口癖だった。
3 5人の子供たち-個性豊かで、バラエティーに富んだ人生-
武治の5人の子供たちは、それぞれ個性に富んだ人生を送った。
長男武(たけし)は、新潟中学校水泳部時代に近代泳法(クロールなど)取り入れ、東京帝大法科卒業後、イギリスの学者・政治家ブライスの『近代民主政治』を翻訳し、晩年は現東京青梅市の山荘で自給自足生活を送った。
長女孝(こう)は、新潟高女時代には短歌を親しみ、大正12年に中村為治と結婚。為治は大学教授・石川島芝浦タービンなど職業を転々とした。昭和20年に乗鞍に疎開して、自給自足の生活を送った。
二男直(なおし)は新潟中学時代に投石で左目を失明するも東京帝大経済学部へ進み、新人会入会社会主義思想に触れ、全日農の運動や小作争議を支援したり、新潟毎日新聞社の労働争議で抗議文を小柳社長に提出したり、しばしば警察に検挙された。昭和5年から東横電気鉄道会社に勤務した。
三男三郎は新潟高等学校から新潟医科大学へ進学、昭和14年満蒙開拓科学研究所員として白系ロシア人のロマノフカ村を調査し2百枚以上の記録写真を残した。北京大学医学院教授時代に2回応召するも、21年に復員し三菱美唄労働科学研究所研究員として炭鉱夫の健康調査に携わった。また、医学生時代からのエスペラント語の知識で昭和6年に『エスペラントの誕生』を翻訳し、平成13年に92歳で『英語・エスペラント語医語辞典』を完成した。
次女正(まさ)は、昭和3年に二葉幼稚園経営の斉藤家の養女となり、新潟高女から東京音楽学校甲種師範科へ進み優秀な成績で卒業後、石川県羽昨(はくい)高女へ赴任するも病で休職し、その後北海道滝川高女に赴任した。戦後は英語教師の資格を取得し、音楽と英語の教鞭を執った。勉強家でエスペラント語の習得にも励み、晩年までスキーを楽しみ、ヨーロッパやアメリカへ何度も旅行をした。山添家で一番活発で人生を楽しんだ。
山添家では、武治と柱(ことじ)のしっかりした人生観により、貧しさを苦とせず、高い教養を身に付けてもそれに満足せず、社会に積極的に貢献することをめざした。5人は学問・スポーツ・思想・旅・言語など自由闊達に人生を謳歌した。その豊かな“ファミリーヒストリー”をたどることは、新潟県の近代家族史の一側面をたどることと言ってもいいだろう。

2019年11月24日 11:06 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
9月例会
令和元年9月21日(土)
新潟の明治開化期イギリス人宣教医師パームの生涯と業績
蒲原 宏氏(本会名誉会員・日本歯科大医の博物館顧問)
〈講演要旨〉
明治初期に来港した外国人医師には、ウイリス、ホイラー、ビダール、へーデン、フォック、ホルテルマン、パームがいるが、一番長く新潟に居り大きな医学実績を遺したのはパームであった。パームはイギリス人、1848年1月22日セイロン島コロンボで生まれ、エジンバラ大学医学部卒業後、エジンバラ医療伝道協会に属し、キリスト教海外伝道医師として1874(明治7)年に来日、翌年4月15日に新潟来住、1883(明治16)年9月30日に去るまで8年6ヶ月医療伝道を行うとともに医学的な調査研究、資料蒐集を行った。
1874年に結婚したメアリー・アンダーソンは翌年の出産時に母子とも亡くなり、新潟在任中の1879年にイザベラ・カラスと再婚、1882年娘メアリーが誕生している。
新潟での医療伝道をみると、明治8年湊町3之町ワイコフ宅、同10年本町通西側吹屋小路下(借地名陶山昶)、同13年秣川岸2で大火に遭い、同14年南浜通2で大畑病院を開業している。大畑病院ではリスター式消毒、看護師養成、クル病・脚気・ツツガムシ病の報告を行っている。明治11年8月13日付けのパームの診断書が残っている。
またパームに学んだ16人の日本人医師がわかっており、その範囲は大畑病院(パーム病院)・長岡・中条・水原・佐渡相川と広がりを見せている。パームは1878年に「ツツガ虫」、1884年に「日本の脚気研究」、1890年に「クル病」と日本の病気についての論文を発表し、クル病については日照不足(紫外線)が主に関係していることを初めて提起している。明治期に発表されたパームの論文は現在においてもその意義が継続している。
私はパーム研究についてエジンバラ医療伝道会に照会し、1972(昭和47)年のロンドンでの国際医学史学会でTOM.RR.TODP医師と会って伝道協会本部のテスター医師を紹介され、パームの書簡等を発見、借り出すことができた。そのなかに新潟での医療現況を著した1883(明治16)年「医療宣教の現況」を発見した。パームは帰国後、イギリスの4カ所で医療活動をし、19の論文を発表した。全英の医師名簿によると1928年に名前がみえないことから没年と考え(1928年1月11日没)、4カ所最後のケント州エレスフォード村の教会、墓地を調査し、現地の老人の助けも借り夫妻の墓とリバーサイドの旧跡を訪問することができた。また昭和52年には最初の妻メアリーと嬰児の墓を横浜山の手外人墓地で発見した。
昭和47年9月に「パーム先生終えんの地を訪ねて」を新潟日報に寄稿。その後パームの娘アグネスからの手紙が届き、同年10月末にロンドンを訪れパームと家族の写真等を見せていただいたが、彼女も昭和52年4月に95歳で没し、パームの家系は途絶えた。
私は今後、伝道会を脱退した背景となった「進化論者の信仰」の翻訳を課題として、教会人としての生命を自然科学者(医師)として断ち切ったパームの業績に迫りたい。
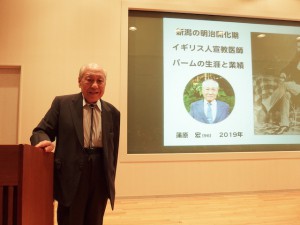
2019年9月25日 9:57 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
8月例会
令和元年8月17日(土)
「開港場新潟」展を観る
新潟市歴史博物館学芸員 若崎 敦朗 氏
<講演要旨>
今日は「開港場」というテーマでお話ししたい。まずはじめに文久2(1862)年発行の地球万国全図という木版刷りの地図に注目したい。日本人の木版技術の高さを示す一例であるが、この地図が頒布されていたことは、日本が当時すでに世界資本主義、市場世界に放り込まれていたことを意味している。
新潟が開港五港の一つに選ばれた要因として新潟上知をあげることができる。天保14(1843)年新潟町が幕府領となったが、幕府のねらいは日本海側での異国船対策の拠点整備と、新潟町からあがる巨額の貢納金獲得にあった。初代新潟奉行川村修就は非常な能吏で、また砲術の名人であった。砲台の設置や大砲の鋳造など関連史料が残されている。
安政の五カ国条約により開港が決定されたが、新潟の開港は繰り返し延期された。それは激動する国内情勢とともに開港準備の不備によるところが大きい。慶応4(1868)年北越戊辰戦争により新潟町は戦禍に見舞われ、町は奥羽越列藩同盟の軍事拠点となり、町民は戦闘から逃れるため近郷へ避難した。
戦争終結後新政府が樹立され、まもなく新潟は県庁所在地、県都となった。そして開港にともない新潟税関や新潟灯台がつくられ、外国との貿易が開始された。しかし、港をとりまく環境不全、冬の風波が強く水深が浅い等々から、大型船の入港は困難で貿易は不振といわざるをえなかった。それに対し国内物資の移出入は盛んで、とくに米、焼酎などが北海道へ移出された。焼酎を入れる容器として松郷屋焼の徳利が活用された。
明治5年新潟県令として着任した楠本正隆は、外国人がみても恥ずかしくない新潟町をめざして開化政策を推進した。町名をわかりやすく変更し、高級住宅、白山公園を造成し、断髪の徹底や盆踊りの禁止など風俗の統制を進めた。同13年新潟に大火が発生し六千戸以上が焼失、近代的建築も含め新潟の町は大きな被害をうけた。
しかし、19年萬代橋が完成、30年沼垂駅開業、31年電灯開始、32年上野・沼垂間開通、34年電話開始、そして同年新潟で一府十一県連合共進会が開催された。それは開化した新潟の街を示す絶好の舞台となった。共進会場に出品された「新潟名所すごろく」には、新潟県庁、県会議事堂、警察署、郵便局などが描かれており、共進会の主催地にふさわしい、都市化された新潟の状況が見事に表現された作品の一つになっているといえる。
(講演会終了後、講師の案内で企画展を観覧した。)

2019年9月13日 9:51 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
7月例会
令和元年7月21日(日)
越後国の預所―預所とは何か?―
東京大学史料編纂所学術支援専門職員 杉山 巖 氏
<講演要旨>
「預所」は歴史的なイメージをしにくいが、以下の3点について、「預所」をとおして近世初期から廃藩置県まで続いた地方制度の特質を考えたい。
1点目、「預所」とは何か?「預所」とは江戸幕府の所領のうち、大名家などに管理を委ねた村々のことである。幕府の直轄支配地である「御料所」に対して、代官所などの運営には経費が掛かるため、規模の小さい所領の場合は、近隣の大名家などに管理を委ねる「預所」を設置した。幕府の所領全体に占める「預所」の割合は1/5以下であった。
2点目、越後国の「預所」は幕末の時点で5,709か村中702か村であった。「預所」を預けられた大名家では、自家の所領の村落行政を行う担当者とは別に、担当者を置いた。「預所」をめぐる事件を取り上げる。まず、預所の村同士の山論について。共に松平肥後守家(若松城主)の「預所」であった魚沼郡の田中村と大沢村との山の用益権をめぐる相論が起こったが、「預所」の村同士の争いは比較的短期間で解決した。しかし、他領との争いとなると解決に時間がかかった。それが、次の丸山興野事件である。信濃川水系の刈谷田川の堤防をめぐって、松平越中守家(伊勢国桑名城主)の「預所」の村々と新発田領の村々との間で幕末に起きた争いであり、「預所」側と新発田領側の代表者が江戸に出て幕末に至るまで裁判を繰り返すが、ついに決着しないままとなった。「預所」を預けられた大名家は、「預所」から年貢を徴収して幕府の御蔵に納めるだけでなく、その村の民政も行わなくてはならなかった。大名家にとって、「預所」は負担と気遣いが大きいものであったことが分かる。
3点目、「預所」の終焉について。明治新政府になり、「政体書」により中央と地方の政治組織の概要が定められた。地方では「藩」・「府」・「県」という行政単位が誕生したが、大名家の預所は、基本的にはそのままであり、明治新政府が成立したにも関わらず、地方の制度は江戸時代とさほどに変わらない状況が続いた。明治3年12月になり「預所」の廃止が決定された。廃藩以前は、線で囲まれた一定の面を一つの行政単位とする感覚に乏しく、江戸時代以前と同様、村落を新政府や旧大名家が管轄する、という感覚であった。
おわりに、「預所」とは何かについて、まとめたい。「預所」とは江戸時代、大名家に管理を委ねた幕府の所領であり、委ねられた大名家では負担に思いつつも、年貢の徴収と管轄地域の民政を担当した。明治3年まで「預所」は存続したが、翌年の廃藩置県により、現在の前提となる線で囲まれた行政区画がようやく実現することになった。

2019年8月4日 5:07 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
5月例会
令和元年5月18日(土)
雑話:新潟湊に現れた異国船と関屋村
―おもに関屋村「安政6年 御用留」から拾う―
本会会員 植村敏秀 氏
〈講演要旨〉
関屋村は、正保国絵図に「関屋村古新田」として初めて見える。半農半漁の寒村で、長岡藩の藩蔵の管理が村の経済的支柱となっていた。海岸砂丘地と信濃川沿岸の低地で、度重なる川欠けと飛砂に悩まされ、集落移転を繰り返していた。
家伝によれば、斎藤家は越前朝倉氏の重臣で、朝倉氏滅亡により越後越前浜へ移住したという。天保10(1839)年ころ、11代斎藤金兵衛が関屋村に移住し庄屋株を得た。安政6(1859)年当時、長岡藩曽根組の坂井郷蔵組に属し、斎藤熊之助が庄屋の任に就いていた。
今日は、安政6年の「御用留」をもとに幕末に新潟湊へ来航した異国船の状況についてお話ししたい。
嘉永6(1853)年のアメリカ合衆国のペリー来航後、日米和親条約で下田・箱館、安政の五力国条約(修好通商条約)で神奈川・長崎・新潟・兵庫を開港した。こうした状況下で、諸外国は新潟湊が貿易港として適当かとうかを判定するために調査船を派遣した。
「御用留」によれば、安政6年4月22日七ツ時新潟湊にロシア船ジキット号が入港し、ボートを下ろし信濃川河口水深を測量し、流作場・山の下に上陸し本町通・大川前通を遊歩し帰艦した。新潟奉行は鶏・山芋などの食料を与えた。23日オランダ軍艦バーリー号が来航し、信濃川河口水深調査を実施、願隨寺で新潟奉行所役人・外国奉行支配調役と会談した。庄屋熊之助は曽根代官所へ報告、番屋建築、長岡藩から者頭・目付・扶持渡奉行・藩兵など30人ほどが来て、庄屋・組頭宅などへ分宿した。その後、諸役協力・私費支出などにより、熊之助は藩から褒美を受領した。
アメリカにかわって日本貿易の中心となったイギリスは、クリミア戦争でロシアと戦う中で、極東での日本の戦略的重要性を重視し、海軍が海図作成を進めた。8月にはイギリス船の新潟湊来航が予見され、「御用留」によれば、9月に入ると長岡藩からの者頭・目付・船奉行・足軽・小者などの関屋村での分宿割り当てが作成され、30日には38人が宿泊し、10月2日に帰城した。
10月9日四ツ時新潟湊にイギリス軍艦アクティオン号とタブ号が来航する。小舟で3人が上陸し、願隨寺で会談し、10日四ツ時頃に出帆した。13日・15日に新潟湊先に現れたが強風のため新潟湊に入港できなかった。長岡藩から防備要員が急遽駆け付けた。イギリス側史料として海軍測量士のブレイクニーの『中国と日本の沿岸で-40年前の-』には、新潟湊の水深が浅く出入港が至難であること、日本側の作成した沿海図が極めて正確であることに驚嘆、評価していることや2隻の船のスケッチや航跡図などが記されている。
安政6年の関屋村では、度重なる風水害や幕末の政情不安の中で、庄屋を中心にたくましく生き抜いていく村人の姿を「御用留」から読みとることができる。
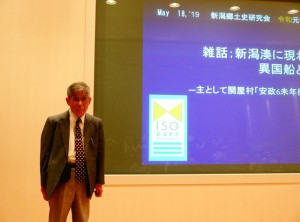
2019年7月28日 11:09 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
4月例会
平成31年4月20日(土)
新発田歩兵百十六連隊少尉弦巻辰三郎氏について
-日中戦争、家族への手紙を中心に-
本会理事 山上 卓夫氏
〈講演要旨〉
数年前笹川玲子さんから父弦巻辰三郎氏の24通の戦地からの手紙を見せてもらった。
第13師団は明治38年に青森で編制、同41年に高田に移り6千名余の軍関係者が居住。この師団には中国留学生蒋介石、レルヒ少佐、師団長に長岡外史・秋山好古がいた。
大正14年国際的な軍縮で13師団ほか4師団が全廃、村松30連隊が高田に移転した。昭和12年盧溝橋事件によって4師団が復活、新発田には歩兵第116連隊が発足。この将校職員表には、片山聞造・小川原潮栄・金子孝信・富山富一、市橋長市・井上慶証など県人の名前が見え、弦巻辰三郎氏は昭和12年に少尉と記載されている。
弦巻辰三郎氏は昭和12年7月26日から同13年10月5日までの間、24通の手紙を妻りき子、父留蔵、子玲子・憲哉など家族宛に書いている。
新潟毎日新聞(昭和12年11月7日)は「両腕に負傷、弦巻少尉」の記事を載せている。氏は中央大学卒業後、新潟医大附属医院勤務中の12年7月応召、新発田歩兵第116連隊に編入、添田隊に属し上海大場鎮の激戦で名誉の負傷とある。入院した呉松病院から出した手紙は昭和12年10月27日付けで妻りき子宛のもので、戦場と負傷の状況が詳細に書かれている。銃創により3本の指で書かれ文字が乱れている。
新潟新聞(昭和13年11月8日)は、我が郷土部隊は頑強な敵と戦い10月14日に大別山の新店に入城、将官では10月11日に2氏戦死・4氏負傷、10月12日では2氏戦死・4氏負傷とあり、12日の戦死者の一人として中尉弦巻辰三郎をあげ、氏の戦死は壮烈を極め小隊を指揮し、真先に進撃と記載している。享年32歳。
翌14年3月10日の新潟毎日新聞は、支那事変戦没者17柱の新潟市葬の記事を掲載。弦巻辰三郎氏は「関屋步大尉」となっており、この頃はまだ市葬を行う余裕があった。辰三郎氏が大別山頂から両親に宛てた昭和13年10月5日付けが24通最後の手紙となった。玲子の手紙がうれしかった、中尉に昇進し第9中隊長となった、大別山で相当の戦死者を出した、漢口陥落を御持ち下さい、僕は益々元気、皆様御達者でサヨーナラと書いた。
講演の最後に映像での紹介があった。家族4人の写真、蒲原神社金子孝信氏の自画像ほか写生画、辰三郎氏が就学前のレイコ・ケンヤも読めるようにカタカナで書いた手紙、新潟市葬における父留蔵の挨拶など。
辰三郎氏の手紙は戦局と時代を反映したもので戦場地名も記されて驚くが、それにもまして、父・母・妻・子への想いが溢れている。戦争に関する史資料は保存・保管され、繰り返し伝えていくことが大切と考える。
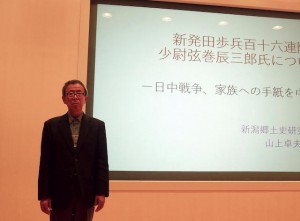
2019年5月4日 6:56 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
« 古い記事
新しい記事 »