3月例会
平成31年3月16日(土)
近世新潟町における廻船問屋津軽屋
本会副会長 菅瀬 亮司 氏
〈講演要旨〉
新潟町の廻船問屋津軽屋(高橋)次郎左衛門家は天明年間(1781~88)、老朽化した長岡藩関屋御蔵の新潟町移転を引き請け重きをなしていく契機となったようだ。その後唐物抜荷事件で財産を費消し明治21年横浜に転居した。関東大震災で関係資料を消失し不明の点も多いが、津軽屋の様相について絵図なども使って説明したい。
抜荷とは密貿易のことで幕府は厳しく取り締まったが、新潟では天保6(1835)年と同11年に事件が発生した。とくに2回目の事件により津軽屋大番頭民蔵や当銀屋善平などが入牢、その後も吟味が続けられた。この事件が以降、同家の衰退につながっていく。
大問屋としての津軽屋は文化7(1810)年の「大問屋申立」に名前が登場している。その後も大問屋として活動し、新潟町奉行の次、検断の上の地位にまでいった。津軽屋繁盛の基礎は6代目次郎左衛門の天明期と考えられるが、9代目の時には新潟町打ちこわしにあい、11代目は抜荷事件に連坐するも放免、14代目は新潟の家屋敷を手放し横浜へ転住するなど、様々なできごとがあった。
津軽屋の屋敷については天明年間、他門通に面した八間小路上角で、大川前四之町と本町通四之町の通し屋敷、間口13間余、奥行46間、地子高は2石7斗2合6勺であった。また享保16(1731)年改めの「家別書附」に「津軽屋次左衛門」の表記屋敷があり、これが津軽屋の屋敷記載の初見であろう。近世期の新潟町絵図や地子帳などから、「高橋次郎左衛門」の表記家屋や「高橋次郎左衛門外屋敷」の記載を見ることができ、津軽屋の外屋敷数は120戸とまではいえないが、かなりの屋敷数を所持していたことがわかる。
津軽屋は三日市藩や村上藩、長岡藩などに大名貸を行い、また天保年間の「越後国持丸鑑」(当時の長者番付)に「東前頭五」として登場している。しかし2回目の抜荷事件以後津軽屋は桜井勘蔵家から資金を借用していたのではなかろうか。嘉永3(1850)年新潟横町浜蔵5か所、白山嶋蔵2か所を売却し、結果的に以前の高橋蔵が桜井蔵に変わっている。
津軽屋の廻船業を石見国温泉津の「木津屋客船帳」から見ることができる。越後の湊からどれだけの船が温泉津に入津したのか、その「客船帳」によれば、18世紀後半から19世紀前半まで新潟湊からの廻船入津総数は108艘、そのうち53艘が津軽屋の廻船であった。53艘の平均水主数は7.6人で、津軽屋は定紋九曜星の船旗で廻船10艘程度を所持し、日本海を舞台に広く活動していたと考えられる。
以上、津軽屋の歴史をたどってきたが、長岡藩との関係などよくわからない部分も多い。今後もご教示をいただければありがたい。

2019年4月2日 3:51 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
2月例会
平成31年2月16日(土)
国史跡「新津油田金津鉱場跡」の価値と特色について
新潟市文化スポーツ部歴史文化課副参事 入江 清次 氏
〈講演要旨〉
今日は「新津油田金津鉱場跡」とはどういうところか、今まで私が見てきたことや聞いてきたことを中心に報告したい。
嘉永6(1853)年ペリーが来航したが、その黒船の黒は蒸気船の石炭タールの黒であろう。石油ランプは開国と同時に西洋から輸入された。最初は街灯などに、その後家庭や工場に普及していった。石油は米国からの輸入が大きかった。
ここに女性が樽を担いで歩いている写真がある。明治期、金津鉱場からの原油を樽に入れ精油工場まで運んでいる写真である。金津から約7キロの道を毎日二往復、2斗2升入りの樽を担いで通っていた人力輸送時代の写真である。
石油の掘り方は手掘りが最初であった。命綱で下に降りていくが、深く掘り進むにしたがって水に苦労した。今も一部分手掘り跡が残っている。明治二十年代に上総(かずさ)掘りが、その後綱式機械掘りが導入され採油量を増やしていった。
現在、金津鉱場跡には上総掘り井戸11、機械掘り井戸13の合計24の油井遺構が残されている。この他、採油の動力源であるポンピングパワーや上屋、継転機、集油所、送油所、各種タンク、加熱炉、濾過池、旧木工所、旧社宅等の石油関連遺構が残存している。このような「新津油田金津鉱場跡」の文化的価値を明らかにするべきとの意見が多く出された。行政として将来の史跡指定を念頭に置き、平成26年度より3か年をかけて文化財としての視点から総合的な調査を実施した。
まず関連する遺構群を悉皆調査し台帳化した。さらに遺構群全体の関係性やシステムも明らかにし、地域に関連する風習や行事、環境などを関連文化財群として把握し、施設配置復元図を作成した。そして同29年度に文化庁へ意見具申し、同30年10月15日国の史跡に指定された。指定担当者から「史跡指定への最短ですよ」といわれたことが印象深く記憶に残っている。
「新津油田金津鉱場跡」は日本の近代化の一端を担った数少ない油田遺跡であり、採油、精製、送油にかかわるシステムが最もよく残る史跡である。しかも地域に密着し、地域と一体となって発展した油田である。国の史跡となったこれからが重要であり、多くの方々から興味、関心をもってもらうことが大切であると考えている。今後も「新津油田金津鉱場跡」をよろしくお願いしたい。

2019年3月9日 8:14 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
新春講演会
平成31年1月6日(日)
地域歴史文化遺産と大橋新太郎・種田山頭火
新潟大学教授 矢田 俊文 氏
〈講演要旨〉
新潟大学附属図書館所蔵の鶴吉村文書と木村家文書は、ともに地域歴史文化遺産として重視したい貴重な史料である。
鶴吉村文書は旧鶴吉村(十日町市)庄屋家が所持していた古文書で、その中に明治期の新潟県治報知がある。県治報知には県令の布達が記されており、その布達内容から、たとえば毘沙門堂での裸押合いは猥らであるので統制が必要である、蒸菓子(饅頭ノ類)の製商にも免許鑑札が必要である等々、当時の村々の生活実態を掴むことができる。
また、同文書の中には「明治二十年度千手校実費支払簿」や「同出納決算」などがあり、これらの史料を分析してみると興味深い点が浮かびあがってくる。それは十日町や小千谷地域の商店が優位でありつつも、大橋新太郎が長岡を拠点にして千手校に小学作文本、尋常科習字本、小学校用軍歌唄本などを納入し、さらに教科書や生徒出席簿、試験表、卒業証書などの学校用品を販売していることである。これはおそらく長岡洋学校で事務掛となっていた父佐平の仕事内容を子供である新太郎が知っていたからであろう。そしてその必要な備品や消耗品を彼が的確に把握していたことが、後の事業の発展につながっていった背景になっていたと考えられる。
木村家文書は近世の平林村(村上市)の庄屋文書を含む厖大な文書群であるが、その中に種田山頭火の自筆書簡がある。それは昭和初期、村上地域で無季自由律俳句グループ「渚の会」が存在していたことが大きい。「渚の会」は昭和6年から同13年頃まで句誌『渚』を発刊し創作に励んでいた会で、『渚』の編集を担っていたのが村上本町小学校に勤務していた木村善蔵(雅号、良二)である。
木村良二は山頭火や自由律俳句の全国誌『層雲』同人らと文通し、山頭火から『渚』の感想などが寄せられていた。昭和8年12月の木村良二宛山頭火の葉書には、『渚』送付のお礼と年の瀬を迎えた現在の心境を記した前書きとともに、「けさもしぐれる 足音は郵便やさん」の句が記されている。山頭火は自身の俳句における前書きは句の構造の一部と考えていることから、この良二宛の葉書は大変重要なものである。昭和11年6月には交流のあった山頭火を村上に招き、良二はじめ「渚の会」の5人が集い句会を開いている。
以上、鶴吉村文書と木村家文書の事例を紹介したが、どのような史料でも磨いていけばさまざまなことがわかり、そして重要な事実が判明していくといえるのではなかろうか。
講演会終了後、恒例の新年会が行われました。当会名誉会長の中原八一新潟市長、歴史文化課長小澤昌己氏から激励のご挨拶をいただきました。

矢田俊文新潟大学教授

中原八一新潟市長

小澤昌己新潟市歴史文化課長
2019年1月27日 1:12 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
12月例会
平成30年12月16日(日)
デューク・エリントンと新潟地震
新潟市美術館学芸員・本会会員 藤井 素彦 氏
〈講演要旨〉
今日は新潟市の戦後期についてお話したい。
来年(2019年)の1月19日に新潟市で第33回ジャズストリートが開催されるが、このイベントには毎回「デューク・エリントンメモリアル」の名称がつけられている。デューク・エリントンはジャズの巨匠である。
私はなぜ新潟で毎年ジャズの催物が行われているのか不思議でならなかったが、新潟の街中を歩いてみてジャズを聴かせる店が多いように感じた。ある意味で新潟は都会であると感じた。それはおそらく新潟の人々が家の中だけにいるのではなく、家の外で過ごす時間や空間が多いのではないのか、その時間や空間にお金を使う文化がまだ残っているのではないかと感じた。新潟はジャズが身近にある街といっていいのではなかろうか。
1964年6月19日、エリントンとそのオーケストラが日本に向けてアメリカを出発したが、その三日前に新潟地震が発生していた。地震発生時セオフィラス・アシュフォードが新潟アメリカ文化センターの第9代目の館長として着任していた。また同年3月には星とよ子さんが館長秘書となっており、二人はともにジャズが好きであった。このアメリカ文化センターは戦後GHQ民間情報教育局所管の図書館からはじまり、アメリカの文化を日本国民に知らせ理解を深めてもらうという趣旨で設けられ、新潟には1948年に開設されていたものである。
館長アシュフォードは地震で甚大な被害を受けた新潟の街を見て、来日中のエリントンに連絡をとり新潟地震救済の話をした。その話を聞いたエリントンは快諾し、7月8日新宿の厚生年金会館でチャリティーコンサートを実現させた。エリントンはすでにハワイ公演の予定が入っていたにもかかわらずそれをキャンセルし、チャリティーコンサートを実現させたのである。聴衆約2,000人、収益金の約96万円が新潟市に寄付された。新潟市は1966年国際親善名誉市民条例を公布、施行し、同年5月ライシャワー駐日大使立会いのもと、条例施行後初めての国際親善名誉市民章をエリントンに贈呈した。
1970年1月エリントンは三度目の来日をはたし全国各地で公演したが、1月10日新潟県民会館でも公演が行われ、多くの新潟市民が彼の演奏を聴くことができた。
エリントンは1971年、旧ソ連でも22回の公演を行ったが、1974年75歳で死去した。彼の人生は働き詰めの人生であったが、すぐれた音楽家であり、同時に高潔な人生でもあったといえよう。(エリントンが実際に演奏している映像も見ることができた。)

2019年1月3日 11:00 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
11月例会
平成30年11月17日(土)
出征兵士から郷里への便り
―銃後からみた大東亜戦争―
本会顧問 中村 義隆 氏
〈講演要旨〉
昭和16年12月に始まった戦争を当時大東亜戦争と言った。私は小学校4年生であったが、生徒も先生も全員が「日本は負けるわけがない、かならず勝つ」と信じていた。そんな戦争の時代に私達は育った。
何十年も前になるが、旧岩室村の公民館を訪ねた時、出征兵士の和納小学校校長宛の軍事郵便が数百通残されていた。その中に昭和20年のはがきが164通あった。月別にみると6月が22通、7月が44通で、この2か月間で半数を占めていた。現地の兵士は負けると感じていたのであろうか。はがきの文面は、故郷の山河や風景が懐かしい、お国のために命を賭して戦いたい、一生懸命勉強してお国のために頑張ってほしい等々、似た文面が多いが、短い文章しか書けないはがきの中に、これが人生最後の便りになるかもしれないという、当時の兵士達の純粋な心情が凝縮されているように感じられる。
「西蒲区和納地区戦没者名簿」によれば、昭和16年から21年までの戦死・戦病死者は70名である。19年が22名、20年が26名で19年、20年が非常に多い。「あそこの人が戦死した」「あの人も戦死した」と、当時「戦死」と聞いても平然とし、いわば慢性化していたと言えよう。
このような戦争を日本はなぜ始めたのであろうか。その答えはなかなか出ない。陸軍軍務局長を務め、戦争推進の中心者であった佐藤賢了氏が自著で「我が日本は米国に操られた、米国の罠にかかった」と書いている。これはどういうことであろうか。
昭和14年に第二次世界大戦が始まり、イギリス、フランスはドイツの侵攻に苦慮しアメリカの参戦を望んだ。アメリカのルーズヴェルト大統領は国内の民意が戦争反対であるが故に日本への強硬姿勢をとり続けた。ハル・ノートにより日米間は破綻しその結果が真珠湾攻撃であった。アメリカ世論は「卑怯な日本を叩け」と国民的一体感を形成していった。
アジアの人々はこの戦争をどのようにみていたのであろうか。たとえばインドにはインド独立のために日本兵はよく戦っていたと考えている人がいる。「大東亜戦争以後のアジア諸国」の地図を見ると、ヨーロッパ諸国から独立した国が多い。もしもこの戦争がなかったならば独立は何十年も遅れていたであろう。現地では「独立とは戦って得るもの」と言われている。
戦争についていろいろな見方があるが、自分で調べ、地元ではどうであったかを検討していくことが重要であると考えている。
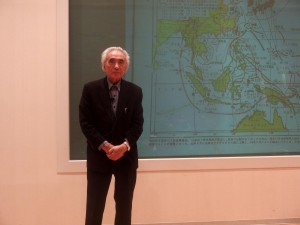
2018年12月5日 7:51 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
9月例会
平成30年9月16日(日)
東蒲原郡の林業について ―近世小川庄の材木、薪炭生産―
新潟県立文書館嘱託 富井 秀正 氏
〈講演要旨〉
私は林野・林業について、とくに関川村や小川庄を対象に調査、研究をしてきたが、今日は小川庄の材木、薪炭についてお話ししたい。
小川庄は現在の阿賀町を中心に、五泉市、阿賀野市、新発田市の一部を含む地域である。寛永20(1643)年以降保科会津藩の支配領域で、庄内は津川町、海道組、鹿瀬組、上条組、下条組に編成されていた。
会津藩の山林は管理、収益の主体が誰であるかによって、御林、地下持ち林、百姓持ち林に区画されていた。また山林に関する役職として、山奉行、郡代・代官、山守が置かれ、漆、桑、明檜、杉、槻、松、黐(もち)の七種類の木については藩の許可を得て伐採しなければならなかった。
小川庄の材木の伐り出しについては、御林の場合無許可の伐採は禁止され、御林内にある雑木でも許可を得なければ伐採できなかった。そして伐採した跡には植林をして林の保全に努めなければならなかった。
明和2(1765)年の史料によれば、小川庄の山守は山奉行所から平堀村地蔵堂原御林の木の販売を命じられ、元木32本を代金180両で販売することを請け負っている。代金は山守と津川商人が出資し、半額を現地で支払い残りは新潟で支払うことにして、材木を川下げしている。このことから小川庄の山守は藩の命令で御林の材木販売に関わっていることがわかる。
宝暦9(1759)年には広瀬村肝煎が小川庄の御林の木が伐り尽くされている現状を見て、御林の保護や植林、材木の伐採、活用の具体策を言上している。なお小川庄では保科松平家入封後、山改めは不要とされた。
材木の伐り出しについて、管理、収益の主体が村や百姓にある場合でも藩の許可を得なければならなかった。そして材木を越後国の者に販売する時には材木改めを受け、役銀が課せられた。たとえば万治2(1659)年室谷村では五葉材木(姫小松)など620本を25両で新潟櫛屋半左衛門に売り渡した。この時も藩の伐採許可を得て、津川で改めを受けている。
小川庄では越国薪(こしこくまき)と呼ばれた薪が生産され、新潟町、亀田方面に販売されたり、綱木村等から新発田町に販売されたりしていた。同時に炭焼きも行われた。焼いた炭は佐渡金山でも使われ、とくに高級な炭は精錬用として使われた。
小川庄の漆は高品質で、会津の漆器生産に重要な役割を担ったが、今回は触れることができなかった。別の機会に是非お話してみたいと考えている。
-300x221.jpg)
2018年10月7日 11:11 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
8月例会
平成30年8月19日(日)
新潟の文明開化と洋方医竹山屯
新潟大学講師・本会名誉会員 蒲原 宏 氏
〈講演要旨〉
竹山屯は天保11(1840)年熊の森(現燕市)の蘭方医竹山甫祐の四男として生まれた。亡くなったのが大正7(1918)年で、今年は彼の没後100年目の年になる。彼は学問全般、とくに医学の分野で、また文化の面でも多くの業績を残しており、彼についての資料をまとめていくことは重要なことであると考えている。
母トミの実家は加茂の森田家で、叔父にあたる森田千庵の影響を強く受けた。また中之島(現長岡市)出身の入沢恭平は義兄にあたり、恭平から多くを学んだ。恭平の弟池田謙斎、恭平の子達吉とのつながりも強く、竹山、森田、入沢三家の家系図を見ると多くの医者を輩出しており、三家の知的力強さを感ずる。
彼は慶応元(1865)年長崎に行きオランダ人教師マンスフェルトのもとで西洋医学を学んだ。軍医ではないマンスフェルトから医学一般を学んだということは重要なことであった。竹山屯筆記のマンスフェルト『中毒各論』が新大医学部図書館に寄贈されている。
明治9年の天皇北陸巡幸の際、新潟に眼病者が多くいるということで1,000円が下賜された。しかしこれは少しできすぎている話ではなかろうか。池田謙斎宛の手紙の中に関連した文章が見られるが、西園寺公望とのつながりの中で有能な官僚のもと、下賜金の準備が事前にできていたのであろうと想像している。
明治21年財政困難を理由に新潟医学校はじめ全国の医学校が廃止となった。しかし同26年近代的医学の必要性を訴え新潟医学校有志懇親会がつくられ、同43年には新潟医学専門学校が開校した。この新潟医専の早期開校実現の背景には、彼や長谷川寛治などの積極的な活動が大きかったと思われる。
明治36年竹山病院が竣工し、新潟市内で最も近代的な病院として発展していった。リバーロッチィー式血圧計を新潟ではじめて導入するなど最先端の診療を行った。また彼は東大医学部の有能な人物に支援を惜しまなかった。なかでも沢田敬義や荻野久作などは世界的な業績を残した医者として有名である。
彼の70歳を記念して出版された『香山古稀集』には、西園寺公望はじめ政治家、医師、学者、美術関係者等々89名の文章が掲載されている。彼の人脈の広さがうかがえる。
彼は日本的な基礎教養を土台としつつ近代西洋医学を学び、西欧の近代合理主義を受容し、地方の文明開化を推進していった一人である。同時に自分をも開明していった努力家でもあった。一人の医者として生きた彼の努力、業績を評価し、その生き方、姿勢に私達はもっと学んでいく必要があるのではなかろうか。

2018年9月13日 9:19 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
7月例会
平成30年7月21日(土)
「にいがた船と港の150年」展を観る
新潟市歴史博物館学芸員 藍野 かおり 氏
〈講演要旨〉
当館では港に関する展示を何回か行ってきたが、今回の展示は船と港について、その形から見てみたいと考え企画したものである。
「西洋形船舶留記」という水戸教の伊藤家が書き残した西洋型の船の入港記録がある。ここには船の外形が描かれ、船型、積荷、経由地、入港日、出港日などが記されている。たとえば工部省明治丸は明治7年イギリスで造られ、灯台が設置されているかどうか点検のための船であった。直江津を経由し明治27年新潟に着いている。また同20年の記録には、函館を経て新潟港沖に投錨したフランス軍艦ヴィペール号と、それに向かっている水先船がともに描かれている。
新潟港は開港したからといって港の形が変わったわけではない。近世以来信濃川左岸が港であった。港口は浅瀬が多く水深が一定でなく、出水のたびに洲の場所が変わった。そのため大型船は沖合に停泊し、艀による荷物運搬が新潟港の姿であった。浅瀬や風浪のためしばしば海難事故が発生した。そもそも新潟港には風や浪をよけることのできる場所がなく、佐渡夷港を補助港として開港された経緯があり、新潟・夷両港を新潟丸・北越丸が荷物運送船として往復した。
明治10年代後半から新潟近海では地元資本による定期的な航路運航が行われた。越佐汽船などにより佐渡夷、直江津、酒田、北海道へと航路の拡大がはかられた。また明治末からは北洋漁業が本格化していった。とくに明治40年日露漁業協約が結ばれ、「日本国臣民ハ……露西亞国臣民ト同一ノ権利ヲ享有スヘシ」と取り決められたことが大きい。このような背景の中で明治期、新潟の人々は近代的な港を造ってほしいと請願を続けていたが、それはながく無視されたままであった。
大正3年になると沼垂側での埠頭建設計画が決定。同6年工事開始。同10年築港事業は県の事業となり、同15年第一期工事が完成した。同時に私営の臨港埠頭が使用を開始し、やがて両埠頭ともに石炭、木材などを取り扱うようになっていった。
県営、臨港両埠頭築港後、定期航路も増えた。昭和7年から大連―裏日本線として大連航路が就航。そして上越線経由で東京―新潟―北鮮―新京の経路が最短となることから、同10年新潟―北鮮航路が政府指定航路となり、13年からは最新鋭船月山丸が就航した。
現在大型クルーズ船の誘致合戦が激しさを増している。東港では17万トン級のクルーズ船が入港できる施設を整備。大型化するクルーズ船をいかに受け入れ可能にしていくか、新潟港としてもその施策が検討されている。
(講演会終了後、藍野かおり氏の解説により企画展を観覧した。)


2018年8月9日 5:27 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
5月例会
平成30年5月20日(日)
北方文化博物館と沢海の風景―伊藤家八代の260年―
北方文化博物館長・本会会員 神田 勝郎 氏
〈講演要旨〉
昭和21年に北方文化博物館が発足し、今年で72周年になる。本日は当館の「営業マン」のような感じでお話ししたい。
江戸時代のはじめ「相見」と記された史料があるが、正保日本図(1644年)には「澤海」とあり、沢海藩が成立した慶長15年ころには「沢海」地名となっていた。
沢海藩は新発田藩主溝口秀勝の次男善勝により誕生した藩で1万4千石。四代まで続いたがお家騒動で廃藩となった。旧沢海藩領は一時幕府領となり、宝永4(1707)年から旗本小浜家が支配した。小浜家の御用達商人となった文吉家は、宝暦6(1756)年仙蔵の倅安蔵が文吉家の養子となり中興し、妻のきよとともに蓄財をなし、伊藤家経営の基礎を築いた。そして二代、三代、四代がさらに伊藤家を盤石なものにしていった。
五代文吉は明治15年邸宅建築のため土木工事に着手。良質の杉材を只見川上流部から購入し、店と茶の間、入母屋二階建の主屋、土蔵門、座敷等を建築し、同20年に完成させた。国語伝習所を卒業した六代文吉は、旧高柳村岡野町の名家村山吉次郎の二女真砂と結婚、三日三晩の披露宴であった。惜しくも彼は同36年33歳の若さで他界した。
伊藤家は代々信用の厚い金融業者として大口の金融を扱い、巨大地主として成長した家である。昭和19年には1372町歩を所有し、その面積は新潟県第一位であった。
七代文吉は明治29年生まれ。慶応大学に進学するも中退し、アメリカのペンシルバニア大学へ留学した。卒業後もアメリカで見聞を広め大正14年に帰国した。戦争終結後の昭和20年9月、新潟軍政部民間情報教育部長としてライト中尉が着任、10月に伊藤家を訪れている。このライト中尉と七代文吉がペンシルバニア大学の先輩、後輩という縁から相互理解が得られ、日本初の私立博物館構想が実現した。それが北方文化博物館である。
ライト中尉は同24年アメリカに帰国したが、八代文吉は当館設立の恩人ライト中尉探しに乗り出し、幸いに同60年アメリカに行きライト中尉と会うことができた。地元紙は「大海に落としたコンタクトレンズを探し出すような奇跡の再会」と報じた。
アメリカ国立公文書館の憲法通りに所在する女性像の台座には、「遺産」(ヘリテージ)と題して「過去の遺産は将来の稔りをもたらす種子である」と刻まれている。今後も北方文化博物館という「遺産」を広く公開し、あるがままの農村文化を多くの来館者に体験してもらいたいと願っている。

2018年6月7日 10:55 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
4月例会
平成30年4月21日(土)
明治の新潟にあったドイツ領事館
新潟県立近代美術館副館長・本会会員 青柳 正俊 氏
〈講演要旨〉
明治の新潟にあった外国領事館の中で、一番長く新潟に所在していたのはドイツ領事館である。しかしその具体的な内容については不明な部分が多い。今日は私が調査をしてわかったことをお話ししたい。
新潟のドイツ領事館は明治2(1869)年9月から同15年10月まで続いた。新潟居留のドイツ商人が何人かいたが、その一人のライスナーが貿易商人であり同時にドイツ領事に任命されていた。当時商人であり領事であるという例は珍しくなかった。
ライスナーは同2年9月横浜から新潟に来た。当初は同国人ウェーバーと共同で交易活動を営んでいたが、同7年仲違いのためかライスナー商会として独立した。「新潟新聞」から同商会が大量の買米を運び出している記事や、火災保険の代理業を営んでいる記事を見ることができる。彼は同15年7月新潟港を出港し、同年8月横浜港から帰国した。
ライスナーがどのような人物であったのか、私は何回かドイツへ調査に行ってきた。彼の手紙などを手がかりに、フランスに近い絹織物業が盛んであったクレーフェルト市の文書館に行き、また彼の弟の三代後の子孫に会うことができた。子孫の家にあった家系図などから、彼が有力商家の一員であり、父親がクレーフェルト市長・郡長を長く務めた官吏であったことを知ることができた。そして彼の母親のヘーニンクハウスと、同11年から15年まで新潟に居留していた商人のヘーニンクハウスとは、おそらく親戚関係ではないかという可能性も想像できた。
4年前ドイツに行き調べたところ、ライスナーが毎年新潟からドイツ本国へ年次報告書を送っていたことがわかった。報告内容は二種類あり、一つは新潟県庁に連絡した内容をまとめた館務報告、もう一つは米がどのくらいとれたかなどをまとめた商務報告である。
報告書には様々な内容が記されているが、たとえばドイツ公使が同14年本国外務省に送った報告の一つに、新潟は「開港としての意味を失い」、港の施設の「工事は当分望めません」などと記された文章がある。すでに外国公使が、政府は新潟港を良くしようという意思はなく新潟の発展はないであろうと考えていたことがわかる。このような外国人の認識の背景の中で、新潟港が次第に閉ざされていくことになったのではなかろうか。
新潟のドイツ領事館は、前半は本町通七番町に、後半は下大川前通三の町にあった。新潟はまもなく開港150年を迎える。その記念としてドイツ領事館跡地に記念碑を建立したいと考えている。記念碑建立に多くの皆様からご協力いただければ大変ありがたい。

2018年5月11日 9:26 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
« 古い記事
新しい記事 »







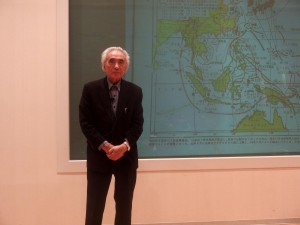
-300x221.jpg)




