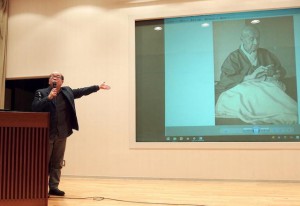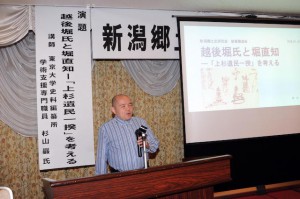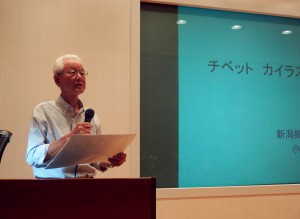3月例会
平成30年3月17日(土)
「江戸幕府編さん史料に新潟市域に住む人々の姿を読む-「孝義録」「続編孝義録料」を基に-」
新潟市総合教育センター嘱託指導主事 後藤一雄 氏
〈講演要旨〉
「孝義録」や「続編孝義録料」は、江戸幕府から善行のために表彰された人々を一覧にした史料である。前者は享和元(1801)年に全50冊で刊行された。後者はその続編(以下の呼称)にあたり、老中牧野忠清(長岡藩第9代藩主)が文化4(1807)年に全国に書上げを命令、嘉永元(1848)年に整理は完了するが刊行には至らなかった。現存の90冊が国立公文書館に保存されている。
表彰徳目は、孝行が主で忠義・奇特・家内睦者・貞節・農業出精などがある。民衆教化政策の一環ととらえることができるが、続編になると収納物篤実・介護・養育・幕府献金・父探索・村方支援・普請などの徳目もみられ、時代背景の違いなどを伺うことができる。
後藤氏は、孝義録の越後佐渡の掲載人物446人(内女性118人)、続編576人(内女性144人)という膨大な史料を整理分析し、特に看過されがちな女性史の視点から再構築し、さらにこの中から新潟市域の史料を例示してお話を展開された。
まず「三島郡尼瀬町ゆり」と「蒲原郡村山村(弥彦村)つじ」の二人の女性をあげる。「ゆり」は寛保2(1742)年に掲載されたものであるが、「越後孝婦伝」として宝暦6(1756)年刊の「越後名寄」に引用され、嘉永7(1854)年・安政5(1858)の版で単著としても流布していた。「つじ」は元文4(1739)年に示達があり、甲斐の孝女と合わせ「越後国甲斐国孝女伝」として同年に版行されている。
さらに氏は、表彰者を越後佐渡の支配別、郡別、身分別、男女別、年令別にも分析され、特に女性の占める割合をみると25%程度であると報告された。小・中・高の教科書に掲載される女性の頻度と比較すると割合が高いとの見解が表明された。
最後に具体的な評伝内容が紹介され、多少類型化な表現も見請けられたが、各藩・代官所などが申請するに当たり熱意を持って表現している事例も伺えた。表彰だから定型の叙述であるとの先入観を超え、評伝内容の検討をとおして社会の変遷や庶民生活の実態にも迫り得る史料として活用できるとの見解は首肯しうるものであった。

2018年3月22日 9:52 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
2月例会
平成30年2月17日(土)
「画家・川村清雄と越後」
新潟市美術館学芸員 藤井 素彦 氏
〈講演要旨〉
川村修就は初代新潟奉行として有名であるが、その孫が清雄である。清雄の高祖父川村修常は元紀州藩士で、八代将軍吉宗の御庭番として紀州から江戸へ来た17人の一人である。有力な幕臣であった川村家は修富・修就・帰元と続き、帰元の長男として清雄が嘉永5(1852)年江戸で生まれた。
清雄が10代~20代のころ、幕末から明治初期にかけては、今までの秩序がひっくり返され、侍の時代は終わったという激動の時代であった。そのことが清雄に与えた影響は大きい。元将軍家徳川家達は駿府に下ったが、奥詰として清雄も駿府に下向した。彼はこのような時代であるからこそ外国へ留学したいと徳川家に願い出、その願いはかなえられた。清雄が20歳のころにアメリカで撮った写真を見ると、彼の目の輝きが印象的である。清雄はアメリカ、フランス、イタリアに行った先々で絵画の修業をしている。英・仏・伊語を巧みに使って学び、華麗な青春時代を海外でおくっていたと考えられる。
清雄はヨーロッパから離れたくなかったが、明治14年日本に帰国した。帰国後大蔵省印刷局彫刻技手となったが、すぐに辞職した。辞職後の窮状を救ったのが勝海舟である。勝は自分の屋敷の一角にアトリエをつくってやり、歴代将軍像を描くよう取りはからってくれた。勝の何回かの催促によりようやく完成した「家茂像」を見て、勝は「そっくりだ」と言ったそうである。清雄は遊んでいるようで実はしっかりと取材をしていたのである。
清雄の絵は和洋折衷といわれるが、彼にとって明治11年のパリ万博は重要であった。出品された日本の美術品は侘び・寂とは無関係な、漆や蒔絵などの高度な技術が駆使された立派な作品で、清雄に与えた影響は大きい。明治23年勝海舟死去後、清雄は「形見の直垂」を描いたが、この絵はいわば清雄の自画像で、清雄と勝との関係には強いものがあった。
勝の曾祖父は今の柏崎から江戸に出て検校の位を得た人である。勝や清雄と親交のあった政治家波多野伝三郎は旧長岡藩士の子供である。豪農市島春城は清雄の「ヴェニス風景」を残した。与板の豪商三輪家11代潤太郎は政治家でもあったが、彼の妹テイ(貞子)は明治25、6年ころ清雄と結婚している(27年離婚)。この三輪家の楽山苑・楽山亭には明るい空間を感じとることができる。西洋の文明を経験した数寄屋趣味とでもいうような、おそらく清雄の趣味がうまく生かされた建築物ではないかと、私は想像している。
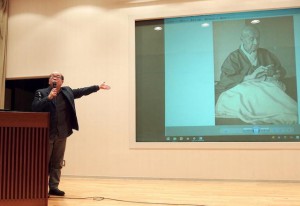
2018年3月11日 9:06 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
新春講演会
平成29年1月14日(日)
越後堀氏と堀直知―「上杉遺民一揆」を考える―
東京大学史料編纂所学術支援専門職員 杉山 巖 氏
〈講演要旨〉
本日は新潟の近世社会の前提となった堀家の時代の歴史的意義についてお話ししたい。とくに慶長5(1600)年に起きた上杉遺民一揆について、その後の社会に与えた影響も含めて考えてみたい。
堀家には堀久太郎家と堀(奥田)監物家の二つの家筋がある。久太郎家は美濃国の武士で織田信長に仕え、信長死後秀吉にも仕え、慶長3年越前国北庄から越後国へ移封となった大名家である。この時堀直政(監物家)、そして与力大名の村上氏、溝口氏らも越後へ移ってきた。堀監物家を興した直政(直寄の父)はもと奥田姓で、堀秀政(久太郎家)の娘を妻とし堀の名字を与えられた久太郎家の重臣であった。つまり二つの堀家は主従の関係であった。
慶長11年堀秀治(秀政の子)死後、子息の吉五郎は元服前であったが、監物家の直政が補佐し、彼が松平吉五郎忠俊と名乗れるまでに成長させた。しかし忠俊は家中を治めることができず、直政死後、直政の子供二人の兄弟喧嘩が起こった。幕府による裁定が下され、忠俊と兄の直知が処罰され、弟の直寄はお咎めなく信濃国飯山城主に移動を命じられた。直寄はその後長岡城主、村上城主となり、越後の近世社会の基礎を築いた人物として高く評価されている。
直寄の兄の実名は、系図によれば直次、または直清と記されている。当初は雅楽助を名乗り、父直政死後は監物を名乗ったが、どの時代の文書を見ても直知と署名している。彼の実名は直知で、直次、直清ではない。
上杉遺民一揆については、新領主となった堀氏の新税賦課に反発する農民たちが上杉氏の時代を慕い、これに乗じた上杉氏の扇動により広がった一揆、そして堀直政らの尽力により平定された一揆と通説的に理解されている。天正・慶長年間、領主の交替と百姓・町人の移動を原因とする大規模な一揆が発生しているが、上杉遺民一揆もその一つと考えられる。社会に与えた影響は大きく、越後堀氏は在方・町方の権利を大きく認める領主として認識されるようになった。とくに新潟町の場合、元和2年に出された直寄の法令を、在方・町方の人々は領主と交渉する際、「堀家から与えられた諸役免除の特権」として最大限に利用した。
郷土史や地域史研究の課題は、その地域のみを考えるのではなく、また日本史や世界史の枠組みをそのまま当てはめるのではなく、地域の歴史資料の分析や研究を通じて、規定の枠組みに再考を促すようなその姿勢が大切ではないかと考えている。
講演会終了後、恒例の新年会が行われました。当会名誉会長の篠田昭新潟市長の代理として、歴史文化課長藤井希伊子氏から激励のご挨拶をいただきました。
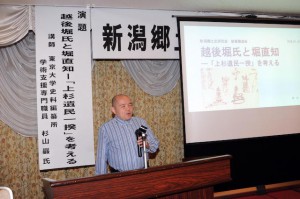

2018年2月20日 9:00 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
12月例会
平成29年12月16日(土)
「ワンダーランド近世新潟町」
新潟市歴史博物館学芸員 小林 隆幸 氏
〈講演要旨〉
江戸時代の新潟町がどのような町であったのか、どのような姿であったのかを見てみたいと考え、「ワンダーランド近世新潟町」を企画した。近世の新潟町を理解するうえで重要なポイントは次の4点であろう。
1.浜を山手という。
2.通りが流れと同じ弧をえがく。
3.海岸からの砂が吹き積もる。
4.沈下しては盛り上がる。
この新潟町は戦国時代にはじまり、今よりも西方にあったようであるが、江戸時代には現在地に近い場所に移転してきていた。400年前の元和3(1617)年長岡藩主堀直寄によって拡張、整備され、その後明暦元(1655)年大きな中州になっていた寄居・白山島に移転した。現在の市街地はこの時に移転、整備された町割りを引き継いでいる。
江戸時代の新潟町の姿は絵図など当時の記録からうかがえる。元禄11(1698)年蒲原新潟立会小絵図や享和元(1801)年頃の新潟絵図を見ると、通りが信濃川に沿って弧を描き、川に沿って町がつくられ堀がめぐらされていることがわかる。品物を載せた小舟が堀を通じて町のいたるところに着くことができたであろう。江戸時代の新潟町は町全体が一つの湊であった。
また、川に沿って延びた通りに面して短冊状に割れた屋敷地が並び、川に近い通りに有力商人の店や問屋が、その奥に職人の店や旅館・料理屋などが、そして一番奥に寺が並んでいる町の構造も知ることができる。
長谷川雪旦の「北国一覧写」には、料理屋での宴会の様子、雁木の町家、障子戸の家、観光スポットにもなっている日和山等、当時の新潟町の具体的な姿が描かれている。
最近、市街地の地下深くから江戸時代の町跡が見つかっている。屋敷跡のほか、多くの焼物や当時の生活用具が出土している。最初に遺物が確認された広小路地点では、地下1.5メートル付近から建物の基礎が見つかった。深い場所から遺物が見つかる原因は地盤沈下のためであろう。広小路地点での調査では、10回以上も土盛りをして屋敷地をかさ上げしている状況が明らかになっている。
明治に入り、楠本県令によりさらに新潟町の整備がなされ、町並みは近代化し変化していった。2019年の新潟開港150周年を目前に、当時の絵図や発掘調査の成果を持ち寄って、江戸時代の新潟町の様子を浮かびあがらせてみることが、今回の企画展の趣旨である。
(講演会終了後、講師の案内で企画展を観覧した。)


2017年12月29日 10:56 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
11月例会
平成29年11月18日(土)
縣立新潟工業学校「學徒日記(昭和十七年度)」を読む
本会会員 石橋 正夫 氏
〈講演要旨〉
縣立新潟工業学校は昭和15年に新潟師範学校内で開校、17年新校舎完成(現日本歯科大学)、21年新制高校の新潟県立新潟工業高等学校となった。
「學徒日記」は、昭和16年に編集・印刷され、生徒が購入したものである。
内容は「五箇条の御誓文」「教育勅語」「開戦詔書」「紀元節詔書」などや年間行事、生徒心得などである。
特徴的な内容としては、「皇国頌」(こうこくしょう)という「愛国百人一首」の中から抜粋された和歌が掲載されている。「愛国百人一首」とは、川田順が雑誌『キング』に連載した古代・中世・近世の歌人・武家や、幕末から日清・日露期までの百首を選んだもので、柿本人麻呂・菅原道真・源頼朝・豊臣秀吉・大石良雄・吉田松陰・西郷隆盛、与謝野鉄幹、軍人では梶村文夫・乃木希典、女性では野村望東尼・松尾多勢子・遊君桜木などの愛国歌から選出されている。翌年には大日本文学報国会が「愛国百人一首」を佐々木信綱・斉藤茂吉・折口信夫らを選者として東京日々・大阪毎日・朝日など大新聞に発表している。大石・西郷らは削られ、徳川光圀・有馬信七・高杉晋作・僧月照らが掲載されている。開戦後であり、全体として「愛国、国威発揚」が前面にでて、君・大君・君が代・天皇という語が入る歌が増えている。
講演では、「學徒日記」の「皇国頌」から橘諸兄・源実朝・梅田雲浜・月照・平野國臣など30首を取り上げ解説した。本居宣長の歌を取り上げて、16年版では、「さし出づる この日の本の 光より 高麗もろこしも 春をしるらむ」だが、17年版では「敷島の 大和心を 人とはば 朝日ににほふ 山桜花」に替わっている。いずれも本来の宣長の意図とは別に16年版は「日本の威光を朝鮮・中国に知らしめる」と、17年版は「桜のようにいさぎよく命を散らす」と曲解して国威発揚と愛国精神を鼓舞する意図があると分析している。また、「愛国百人一首」は17年以降、山田耕作などの有名作曲家によりメロディーが付けられて、教育現場で皇国精神高揚のための小学唱歌として歌われることになったと指摘している。さらに、山本五十六が真珠湾攻撃の直前の16年12月3日に「大君の 御楯とただに 思ふ身は 名をも命も 惜しまざらなむ」の歌や「皇国頌」の末尾の兵士の歌「父の子ぞ 母の愛子ぞ 御軍に よわき名とるな 我が國の為」などを紹介して、戦争になだれ込んでいく時代精神を解説した。
講演では、様々な写真資料が活用され、戦中から戦後にかけての学生生活や学校建設のようすがわかりやすく再現されていた。なお、講演に使用された資料は、長橋昭一郎氏と渡辺馨一郎氏より御提供いただいたものである。

2017年12月7日 8:42 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
9月例会
平成29年9月17日(日)
都からみた越国
本会会長 伊藤 善允 氏
〈講演要旨〉
天地開闢からときおこす「古事記」「日本書紀」は、8世紀に編纂された歴史書である。編纂された歴史ということから、編纂当時の貴族の意識が反映されており、そのまま史実とみることはできない。今日は「古事記」「日本書紀」の記述を追いながら、そこに描かれている古代の世界、そして編纂者たちの意識をさぐっていきたい。
国生み神話について、日本書紀は「一書に曰く」として異なる伝承を多く載せており、「島生み神話」がもとになっているといわれている。佐渡は必ず出てくるが越国が出てこない伝承もある。越も島として認識されており、未知の、未開の世界として意識され、山々をこえたかなたにある「大倭豊秋津島(大日本豊秋津洲)」とは別の概念の地ととらえられていた。
大彦命が高志道(北陸)に派遣されたとする四道将軍の話は、大和王権の勢力拡大の過程で生まれたとされており、出雲国風土記には大穴持神が「越の八口」を平らげたとする伝承がある。越後国風土記逸文にみえる「八掬脛」は「土蜘蛛」と同類で大和王権に服属しない存在であった。ヤマトタケルの東征阿倍比羅夫の北征にみられるように、貴族の認識としては、日本列島は弧状ではなく東に蝦夷がおり、越は北の地ととらえられていた。
八千矛神の沼河比売求婚の話は、越後国風土記逸文にみえる「八坂丹」は青八坂丹の玉すなわちヒスイを求めての話ともいわれており、また、出雲国風土記に越国に関する伝承がみられ交流があったことが知られ、日本海沿岸に気多神社あることなどから「気多政治圏」があったとする説もある。
「古事記」「日本書紀」について、歴史学・神話学・国文学・民族学・民俗学など様々な立場からいろいろな解釈がなされており、どれが正しいのかよくわからない。研究という立場を離れて神話・伝承を「物語」として読んでいくと、また違った楽しさ、おもしろさをみつけることができる。

2017年11月23日 8:46 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
8月例会
平成29年8月20日(日)
新潟県内の道路元標―保存にむけて―
本会会員 渡辺 等 氏
チベット・カイラス巡礼の旅
本会会員 小熊 英雄 氏
〈渡辺等氏の講演要旨〉
道路元標は大正年間、全国の市町村に置かれた道路の起点終点を示す石柱である。大正9(1920)年の第1回国勢調査報告によれば、新潟県の自治体は3市43町369村、合計415の市町村があった。そのうち私が現地を探訪して確認することができた道路元標は、平成29年6月30日現在総計207基で、内訳は残存しているもの179基、土中に埋まっているもの2基、以前あったというもの26基で、確認率は49.9%である。
私が道路元標に興味を持ち始めたのは、旧松ヶ崎浜村で「気になるもの」に出くわして写真におさめ、それが「道路元標」というものであると知った時からである。さらに新潟県庁に問い合わせたところ、担当の方から熱心に対応してもらったことも大きい。過去の何回かの市町村合併により失われた道路元標も多いが、市町村の移り変わりを後世に伝える重要な資料の一つであり、調査し保存しなければならないと考えるようになった。
慶長9(1604)年日本橋脇に里程標を立てたのが道路元標の始まりと伝えられている。その後各地に里程標が立てられるようになったが、旧会津街道をはじめ一里塚が残されており、歴史保存の方策が考えられている。大正から昭和十年代くらいまでに生まれた人で道路元標を記憶している人がいるが、ほとんど忘れ去られた存在になっている。
私は県内の旧415市町村を訪ね歩き、半分ほどを確認できたが、今後も道路元標の調査、探訪を続けていきたい。

〈小熊英雄氏の講演要旨〉
私は平成6(1944)年、62歳の時にチベット・カイラス巡礼の旅をした。それは定年退職後の一つの願いでもあった。4,000~5,000メートルの高原の旅ということで医師の診察を受け合格し、全国から5名の仲間(うち女性1名)の一人として参加することができた。旅のきっかけは河口慧海師のチベット旅行記に出会ったことである。
日程は7月31日から8月24日までの25日間、行程は成田―香港―成都―ラサ―カイラス―カトマンズ―香港―成田の合計3,000キロ、徒歩52キロの旅であった。
チベット・カイラス山は信仰の山、巡礼地であり5色の祈祷旗が峠にたてられている。マナサロワール胡を見てインダス川の源流に行き、抜けるような青い空、そして虹の奥に聳えるカイラス山を見ることができた。ヤルツアンポ渡河に際しては水嵩が増え渡れないトラブルがあったが、地元の人びとから回り道を紹介してもらい無事通行できた。
私がカイラス山巡礼最高地点のドルラ(峠)を目指し、砂礫の坂道を歩き続け道端に腰を下ろしていた時、チベット族の親子が「元気を出して」と目で合図をし一かけらの氷砂糖を差し出してくれた。私は思わず「ありがとう」と両手でいただいたが、親子は何事もなかったかのように去っていった。貴重な氷砂糖を私に与えてくれた行為は「自利・利他」の行為であり、まさにお釈迦様の教えそのものではなかろうかと感じた。
私にとって冒険的要素の濃い旅ではあったが、貧しいけれど豊かな世界に生きる人びと、そしてそこであたりまえに生活している人びとに接し、忘れることのできない旅であった。
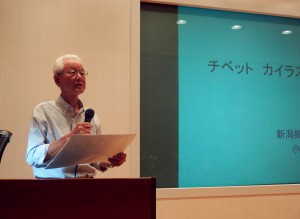
2017年9月8日 1:25 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
7月例会
平成29年7月15日(土)
「乙女たちの歩み~新潟の女学校と女学生」展を観る
新潟市歴史博物館学芸員 藍野 かおり 氏
〈講演要旨〉
新潟市政令指定都市・区制施行十周年記念の企画展「乙女たちの歩み」展が今日オープンした。この企画展は、女学校や女学生を通して女性がどのように社会とかかわったのか、どのような役割を担わされたのかを考えてみようと、企画したものである。
展示内容を六つの章に分けてみた。「新潟における初期の女子中等教育」「開校した女学校での学びと暮らし」「設立が相次いだ高等女学校と新しい教育」「女学生の卒業後の経路」「戦争に向かっていく中での女学生の対応」「戦後の教育改革と女学校」―この六つを各章のテーマとした。
今日は高等女学校の制度とそれがどのように広がっていったのかについて触れてみたい。
明治32(1899)年高等女学校令が発布された。明治政府は「女子に須要なる教育を授く」場として、各道府県に道府県立の高等女学校を少なくとも一校開校させることを義務づけた。新潟県は同33年新潟市に新潟県高等女学校を開校させた。
同40年の「新潟県立新潟高等女学校規則」によると、修業年限は4年、尋常小学校卒業以上を入学資格とし、授業は週30時間、学科目は裁縫、家事科、教育、手芸などであった。男子の中学校で行われていた博物、法制、経済、実業の授業はなく、また英語、数学の授業時数は中学校の半分であった。
同43年高等女学校令の改正で、実学を重視する「実科高等女学校」の設置が認められた。その設置は地域の事情により高等小学校との併置が可能であった。
大正2(1913)年巻町に、同9年新津町に実科高等女学校が開校した。この2校は同年高等女学校に組織変更され、後に県立に移管した。同11年には亀田町、同12年には白根町に高等小学校併設の実科高等女学校が開校、新潟市でも同10年市立実科高等女学校が沼垂尋常高等小学校卒業に併設され、同14年高等女学校に組織変更、校舎が新設された。
このように明治・大正期、教育機会の拡大を望む地域の声に応じて「実科高等女学校」が設置され、それが組織変更されることによって「高等女学校」が広がっていった。同時にそのことが学校設備とともに女子教育の内容充実にもなっていったと考えられる。
今回の企画展で、女子教育や女学生の変わった部分と変わらない部分、この両方を見ていただけたらありがたい。
(講演会終了後、藍野かおり氏の案内のもと企画展を観覧した。)


2017年8月7日 9:45 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
5月例会
平成29年5月21日(日)
小林存を追う
―新潟市学校町天神様の小林存歌碑をスタートに―
本会会員 大谷 晴夫 氏
〈講演要旨〉
新潟市学校町の天神様境内に、小林存の「里川にメダカ掬ひて遊びたる遙かなる日のまぼろしに立つ」の歌碑がある。これは田澤喜一氏が個人で建てた歌碑であるが、私は幼少の頃から学校町に住んでおり、また小林存も学校町に住んでいたということで興味を持ち、彼を追いかけている一人である。
今年は小林存生誕140年、没後56年になる。小林存の業績や人物像、年譜等々については、すでに多くの人々により明らかにされているが、私は彼の佐賀中学校教師時代の年代についてはっきりさせたいと思っていた。それは川崎久一『小林存伝』の年譜に「明治29年11月県立佐賀中学校の英語教師として赴任、31年同校を辞して帰郷」と記さているのに対し、大正12年2月4日発行の「東北時報」小林存「自叙伝」には「明治三十一年二月赴任、三十四年春辞職」と記されているからである。
そこで私は佐賀県立佐賀西高等学校(旧県立佐賀中学校)に問い合わせたところ、同校の「教員履歴」には「明治三十二年一月十六日赴任、三十三年六月十八日辞職」と記されているとのことであった。実際明治32年1月21日の「新潟新聞」に「小生今回佐賀県第一尋常中学校へ赴任し爾今左記の處に寓居す…佐賀市会所小路吉田方 一月二十一日 小林存」の記事があり、また佐賀県第一尋常中学校栄城会「栄城」第6号(明治32年4月30日発行)にも「小林存 佐賀県第一尋常中学校教諭心得ヲ命ス(一月六日)」とあり、小林存の佐賀中学校赴任は32年1月であることがはっきりした。私は佐賀市へ行き、彼の下宿先住所を確認し、感慨にひたりながら歩くことができた。
小林存の新潟居住地については何回かの転居があるが、昭和2年の「新潟新聞」記事に「学校町北辰学館向小路」、同9年の記事に「学校町二番町」とあり、昭和に入り学校町に居住していたことがわかる。北辰学館向は岡本小路近辺のことで、山田又一の随筆集『ひとりしずか』には小林存、山田穀城(花作)、広橋足穂が居住していた「学校町文芸小路」として紹介されている。小林存は昭和14年から19年まで(17年という史料もあるようであるが)町内会長を務めていた。
小林存一家の写真が残されている。「存さんは三世代いっしょに住んでいた。楽しく過ごしていた」と聞いている。今回は小林存の思想的中味に触れることができなかったが、今後も彼を追いかけながら究明していきたい。
講演終了後、この会に参加されていた蒲原宏氏(本会名誉会員)に、司会者より「小林存についての想い出などをお話しいただけたらありがたい」という要望があった。(以下、蒲原氏のお話の要旨)
小林存の活動や研究、業績を振り返ってみると、内容が多彩で豊富、いずれも優れたものである。特に民俗学の研究や「高志路」の編集、発刊には偉業というべき面があると思う。私は「高志路」の編集のお手伝いをしたことがあるが、どのようなやりくりで財政が執行されていたのか、今も不思議な感じがしている。おそらく小林存という「人間性」でやりくりされていたのではないかと想像している。
病気で倒れられた時、私は主治医の一人として当時の病院で治療に当たったことが印象深く思い出される。70歳前後から短歌を詠まれたが、短歌の面でも大変才能があったと思う。今あらためて偉大な人物であったと実感している。

2017年6月3日 8:38 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
4月例会
平成29年4月15日(土)
村役人になるまで ―新発田領の村役人の〈勉強〉と往来物―
本会会員 杉山 節子 氏
〈講演要旨〉
私は旧大江山村(現新潟市江南区)出身で、父は田村順三郎である。父は365日調べものをし、常に原典にあたり古文書を読んでいた。私は父といっしょに周辺村々を巡りいろいろなことを教えてもらった。退職した今、父の想い出とともに歴史をやりたく図書館に通い研究しているところである。
新発田領では郡奉行・大庄屋の下、有力農民の村役人が村落行政に大きな力を持っていた。村役人は単なる「読み・書き・算盤」以上に行政文書を処理する能力が必要であった。村役人はどのようにその力を身につけていったのであろうか。田村家に遺された往来物を手掛かりに見ていきたい。
田村家は江戸時代の中期、宝暦11(1761)年より蒲原郡茗荷谷新田と江崎新田の名主を務め、藤山村の名主を兼務し幕末に至った家である。宝暦11年以前から藤山村の名主で大庄屋小林家の手代でもあった。
田村家の文書群は現在新潟市歴史文化課に所蔵されているが、この中に39点の往来物が遺されている。往来物とは往復書簡の形式をとった庶民教育の教科書である。遺されている39点の往来物を見ると、文字や単語、教訓、歴史、地理、農業など内容は多岐にわたるが、横越島周辺の地名が記され編集されたものがあり、これを手本にしながら周辺地域の状況を学んだのであろう。また「田村喜惣次 十壱才」と記されたものもあり、十代前半ですでに往来物を学んでいたことがうかがえる。さらに溝口家の三種類の法令集が記されているものや、地元寺院とのやり取りの手紙が記されたものもあり、往来物は地域の歴史をみていくうえで重要な素材を提供してくれる。
39点の往来物のうち33点が写本、6点が版本である。版本6点の中の一冊は水原で購入したもので、当時の大江山地区は書物に関して水原の商圏であった。また別の一冊には旧蔵者と思われる「水原上町 豆腐屋友七」の署名があり、田村家はこれを古書として水原で購入したものと考えられる。
その他にも、表紙の裏として横越組大庄屋建部・小林両家の連署状が使用されているものや、行間に「天明6(1786)年大水のために米価が高騰した」などの書き入れがなされているものもあり、多くの情報を読み取ることができる。
このように、各地、各家々に遺された往来物を比較研究することにより、地域の歴史を探る貴重な手掛かりが得られるのではなかろうか。

2017年4月30日 7:16 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
« 古い記事
新しい記事 »