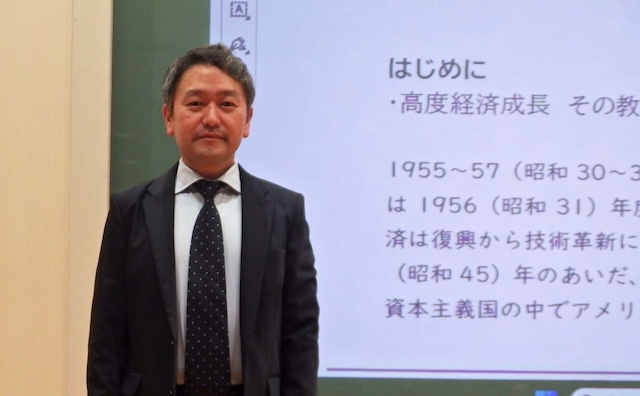4月の例会=報告
4月例会
令和7年4月20日(日)
日本近現代史研究の観点から考える高度経済成長前期の新潟市政
新潟大学人文学部教授 中村 元氏
<講演要旨>
1950年代から70年代にかけて日本は高度経済成長の時代であった。その前期、50年代の動向について考えてみたい。そしてこの時代の新潟市政をどのように捉えたら良いのか、という視点からお話したい。
戦後の日本経済の回復は速かった。それは国民の勤勉な努力によって培われたが、その成長は「戦後の終わり」をも意味した。しかし近代的大企業の経営と同時に、前近代的小企業及び家族経営による零細企業や農業も存在し、いわば一国に先進国と後進国が併存する二重構造の状態であった。そして日本は世界的な動向を背景に完全雇用の政策も掲げ、50年代はその二重構造と完全雇用の二つの克服をめざした経済成長が大きな課題であった。
50年代鳩山一郎内閣、岸信介内閣により長期の経済計画がたてられたが、その中で国民所得倍増計画も立案されていった。この計画とともに、太平洋ベルト地帯を中心とする既存の主要工業地帯に重点投資する成長路線は、所得格差、地域格差、過大都市の発生等々の諸問題を浮上させた。その結果格差是正の方策や産業立地のあり方などが議論、検討され、地域間の均衡ある発展という方向性がとられるに至った。
51年新潟市は工場誘致奨励条例を制定し、工場の新設や拡充策を打ち出した。47年から59年まで新潟市長であった村田三郎は、新潟市議会で「工場誘致は将来の新潟の資源である」と答弁している。新潟市の工場誘致には有利な条件があった。天然ガスの存在である。新潟の天然ガスは化学工業の主原料として着目され、新潟市が商業都市から工業都市へと大きく転換する重要資源であった。しかし57年頃より新潟市の地盤沈下問題が取り上げられ、その原因の調査や対策事業等で厳しい財政難に直面し、さらに天然ガス採取規制により工場誘致は頓挫せざるをえなかった。
このような中、60年池田勇人内閣により国民所得倍増、過大都市抑制、地方への産業分散対策が発表された。新潟市長渡辺浩太郎はその動きをとらえ、国の公共投資や融資、税制優遇措置を利用する積極的な経済振興構想を表明した。62年国の重要政策として新産業都市建設法が制定された。翌63年新潟地区も新産業都市の指定を受け、64年3月正式決定された。その決定後新たな建設に着手しようとしていた同年6月、新潟地震が発生、新潟市はすべての面で災害復旧に取り組まざるをえなかった。そして経済振興推進の道も中断を余儀なくされた。
以上、50年代から60年代の新潟市政を見てきたが、この時期の新産業都市建設に向けた開発と新潟地震による震災復興とがどう交差したのか、今後の検討課題であると思われる。