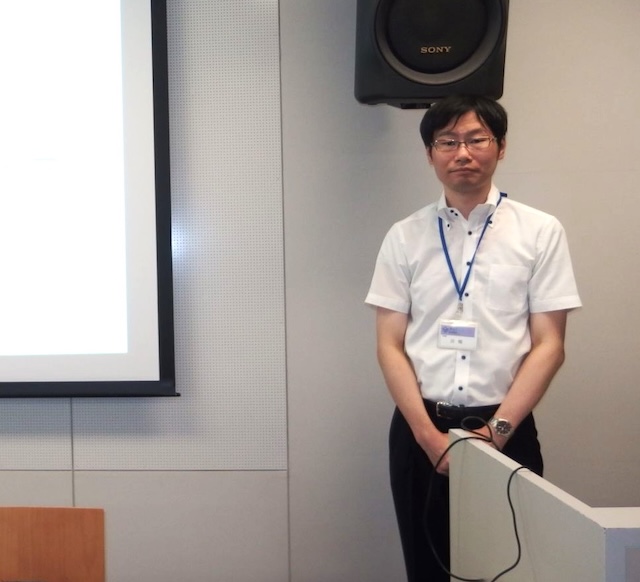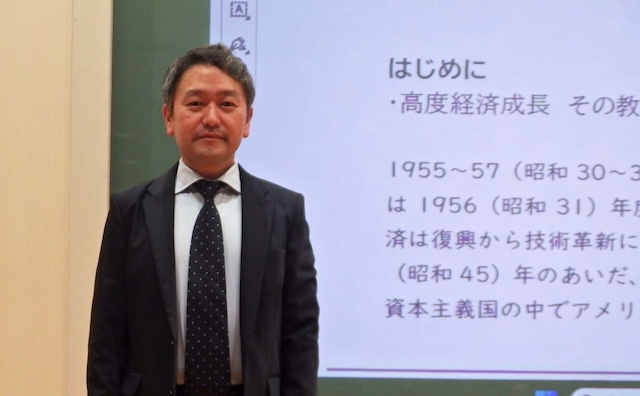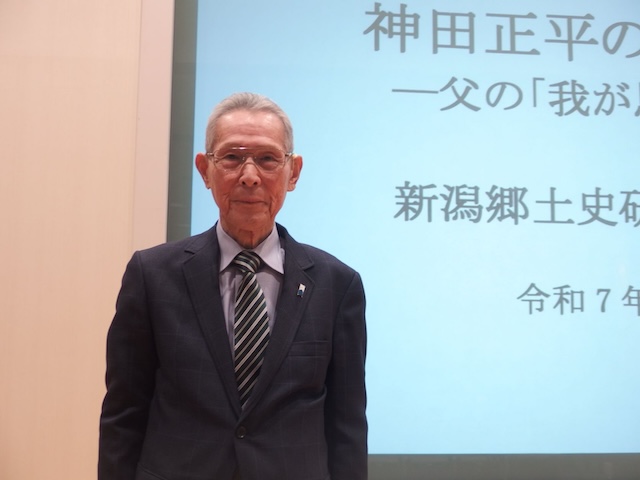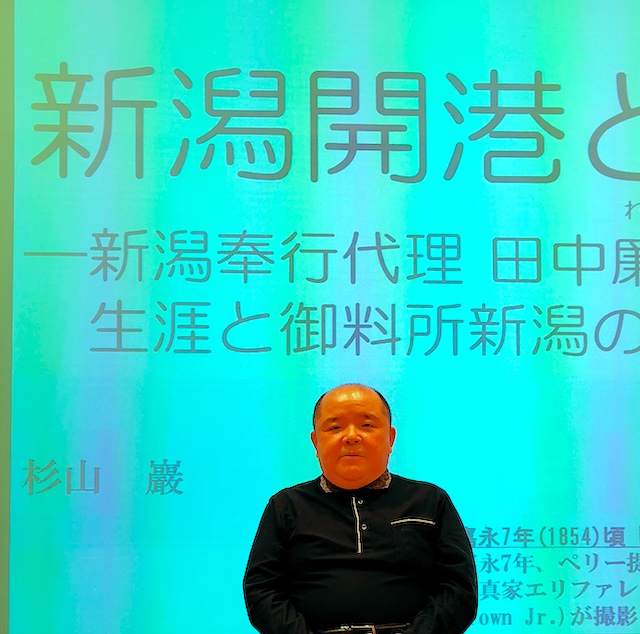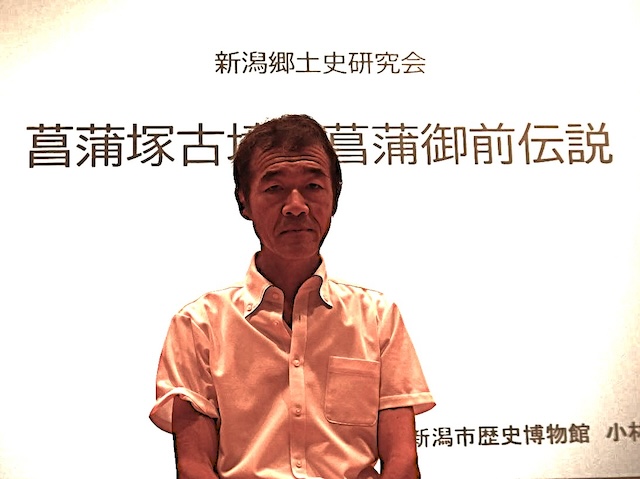8月例会
令和7年8月17日(日)
「近代新潟における歯科医療のあゆみ」
当会会員 日本歯科医史学会会員 広瀬 秀(ひでる) 氏
<講演要旨>
はじめに昭和22年生、新潟下町育ち、歯科医。大学卒業後6年間福島で学生教育と研究生活、日本歯科医史学会入会、遺跡発掘にも参加。帰郷後は父親が新潟郷土史研究会発足時のメンバーであった同会入会、新潟大学考古学研究室の調査員として活動と紹介。
まず古代・中世の歯科医療としては、BC5Cの「ヒポクラテス全集」に歯の出来方、医療について記載があり、紀元前後のケルズスは器具や口腔衛生を説いている。魏志倭人伝に「黒歯国」の記載、大宝・養老律令に「医疾令」の条文がみえる。中世西欧では理髪師による治療や外科医の抜歯例があった。わが国では室町期に口中を治療する口科医・口中医が存在し、天文7(1538)年没の中岡テイの木床義歯の事例があり近世初頭には入れ歯師の生業があったと思われる。
近世になると「救民妙薬集」(文化3,1806年)や「江戸買物独案内」(文政7,1824年)など歯痛薬や民間薬処方の出版も行われた。また松尾芭蕉や小林一茶の歯痛や知覚過敏に悩む作句もあり、江戸期の頭蓋骨からは歯周病の所見がみられ、貝原益軒は「養生訓」で歯の健康維持法を説いている。
新潟における歯科医療の黎明には外国人歯科医師来日の影響がある。その嚆矢はウイリアム・クラーク・イーストレーキで、慶応元(1865)年来日、明治16(1883)年再来日、歯科医院を開業する。明治7年来日の歯科医師メーソン・パーキンスの日本人門下生のなかで山田利充と黒田虎太郎は新潟に縁がある。山田は明治16年東京で開業、同27年に長岡町で開業した当県最古参の歯科医師。黒田は高田町生まれ、明治10年渡英し歯科医学を学び、16年に歯科医術開業試験に合格し政府の開業免許を受け横浜で開業。ほかに新発田町の佐藤家は今日まで9代歯科医師であるが、3代は新発田藩の御抱え大工、4代は普請奉行、5代は口中医、6代が明治30年医術開業歯科試験に合格している。
医師・歯科医師の医療を向上せしめた制度が明治7年の医制であった。従前の怪しげな医術開業者を排除し、国が認可する医術開業試験を受けさせ、開業免許を与える現在の国家試験の前身のようなものである。明治8年に初の医術開業試験が実施された。この時歯科の概念はなく「口中科」での受験であった。同12年に「歯科」の科目が制定された。当県での初めての合格者は長谷川友治である。中蒲根岸村の出身で新潟医学校で学び、明治15年合格、同年末に新潟町で開業、新潟市最古の歯科医師。明治16年には新しい医師免許規則が制定され医術開業歯科試験が実施された。
高山歯科医学院はわが国最古の歯科医学教育機関。設立者高山紀斎は備前岡山藩出身、明治5年アメリカで歯科医学を学ぶ、同11年東京で高山歯科診療所を開業、同23年高山歯科医学院設立、同32年高山歯科医学院の経営を血脇守之助に譲る。同40年東京歯科医学専門学校に昇格、昭和21年東京歯科大学発足に続く。
血脇守之助は明治3年我孫子在出生、慶應義塾入塾、明治23年三條町米北教校の英語教師、同26年高山歯科医学院入学、開業歯科試験合格、高山紀斎から学院経営を継承。血脇守之助は高山歯科医学院学僕の野口英世と石塚三郎を出会わせ、ふたりは生涯の友となる。石塚三郎は明治10年安田村生、同30年高山歯科医学院採用、医術開業歯科試験合格後33年長岡市で開業。地域歯科医師会の設立に尽力、初代新潟県歯科医師会会長に就任。平成13(2001)年に新発田市佐藤泰彦医師によって「石塚三郎日誌及び会計簿」が発見された。終わりにこれからの歯科医療について見解の開陳があった。
2025年8月24日 5:55 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
7月例会
令和7年7月13日(日)
「戦場の町と村 新潟市と戊辰戦争―新収蔵山口家資料を中心に―」
新潟市歴史博物館学芸員 田嶋悠佑 氏
<講演要旨>
令和3年春に山口家資料寄贈の打診があり、実物資料も併せて受け入れる条件で当館への寄贈となった。このことが本企画展のきっかけとなった。
山口家は蒲原郡山口新田(西蒲区)を開墾したと伝えられ、代々庄屋を務めた。今回取り上げるのは幕末・明治期に生きた山口謹一郎(1841~1890)に関する資料である。
慶応4年(1868)1月3日に鳥羽・伏見の戦いが勃発し戊辰戦争が始まる。戦争開始により会津藩が討伐対象とされる一方、幕府が越後の水原代官所所轄領を会津藩に引き渡したため会津藩の越後進駐が行われ、5月には米沢藩の越後への展開も始まる。6月1日には新潟町の施政権が米沢藩総督色部長門に委譲され、米沢藩を実質的な核として列藩同盟が新潟町を管理することになった。色部長門の日記によると、慶応4年6月10日の条に「山口謹一郎召し出す」とあり、両者の関係が初めて見える。6月28日には岩船郡下関に謹一郎が派遣されている。色部長門の家臣石山源内の記録にも謹一郎の動向がみえる。7月9日には光林寺(色部の駐屯所)に謹一郎が来て酒をふるまわれている。7月25日には太夫浜に新政府軍が上陸したため、謹一郎ら3人が物見に派遣されている。
次に山口家資料にみえる状況を示す。7月19日の覚には「謹一郎を兵隊隊長に任じ、士分とする。勝利後に禄知を与える」と記されている。7月の宛行状には「国替以来山口新田を開発し、庄屋を務め、米沢藩の動員に応じたことを賞し、三人扶持を与える」としている。同じく7月の朱印状では忠節を賞し、禄知を与えることを約している。8月の願書は山口新田の百姓41名が新政府民政役所に謹一郎の助命を嘆願したもの。8月4日の長州藩福原又市の書状には謹一郎が福原に会い酒を酌み交わしたこと、恭順し武器を渡す約束をしたことが記されている。8月11日の覚は福原の使者藤宮三九郎が謹一郎から渡されたゲベール銃50挺・刀9本の受取状である。旧式のゲベール銃ということからもわかるように、米沢藩があまり性能のよくない武器を支給していたことがうかがえる。
戦争を通しての謹一郎の位置づけを次に示す。謹一郎は幕末の政情不安を受けて政治運動への参加を志し、戊辰戦争の勃発を受けて米沢藩に属し、従軍した。しかし、米沢藩は謹一郎を取り立てるも武士とは一線を画した扱いをする。現実を知った謹一郎は早々に降伏し、以後は庄屋としての技量を生かす形で明治の世を生きていく。
山口家資料は戊辰戦争に参じた人々がどのような人生や背景を持っていたかをより詳しく明らかにしてくれる。資料所蔵者とのコミュニケーションや地道な資料整理作業がよい成果を生む。博物館のそうした仕事にも注目していただければありがたい。
〈この後、展示解説が行われた。〉
2025年7月21日 12:13 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
5月例会
令和7年5月18日(日)
越後人がアフリカの南スーダンで橋を作った話
建設技研インターナショナル 当会会員 梅田典夫氏
〈講演要旨〉
2022年5月に南スーダンのナイル川に560mのFreedomBridgeが架けられた。この架橋工事は2013年8月から始まり、紛争やコロナ流行による中断を経て、ようやく完成した。2014年1月から常駐監理者として、ずっとこの工事に関わってきた。
スーダンは、1956年にイギリスから独立した。しかし、北部のアラブ系イスラム教住民が政権を掌握し、南部の黒人系キリスト教住民は従属的な地位に置かれ、南部は経済的にも開発が遅れた地域となっていた。そのため、南部で分離独立運動が起こり、2011年7月9日に南スーダンとして独立を果たした。
国を南北にナイル川が貫くが、橋は老朽化した仮橋が一方架かるだけで、ケニヤの港から運んだ物資を、首都ジュバや西部地域に輸送するのに支障があった。そこで日本政府は南スーダンに無償援助として近代的な鋼橋を提供し、経済発展の基礎となる流通発展に寄与するインフラ整備を行うこととしたのである。
工事は大日本土木(株)が担当し、日本から世話方となる職人10人ほどが現地に入り、現地の作業員200人ほどを雇用して、仕事を指導しながら作業が行われた。工事は想定外に硬い岩盤への対応や河川中への橋脚建設など困難なことがあったが、日本人の技術力や現地の人々の正確な測量などによって完遂することができた。
こうした大規模な近代的な土木工事は南スーダンでは初めてのものであり、工事を実施したこと自体を南スーダンにとって有意義なものとするために、様々な取り組みを行った。作業員に、自分の仕事が単に日々の糧を得るためのものではなく、いかに社会的意義を持っているか認識して働いてもらう。工事を進める上で必要な規律、時間、安全の厳守などを体得してもらい、日本の職人たちの下で技術と要領を学び技術移転を円滑に行う。この点、南スーダンの人々は素直で呑み込みのよい人々であった。また、現場で学んだ南スーダンの土木技術者に、この橋の工事を素材に学生へ講義してもらい、講演者、聴衆者ともに土木技術意義への理解を深めてもらい、土木専攻の学生には現場視察も重ねてもらった。現場近くの小学生には土木への興味を持ってもらい、将来の国づくりに寄与できたらと現場見学をしてもらい、あわせて橋を架けている日本という国への理解を深める活動も行った。
つまり、FreedomBridgeの架橋は、単に構造物の無償供与というだけでなく、これから南スーダンを自立的に発展させていくために必要な技術移転や教育などにも役立ったと考えている。ただし、FreedomBridge一橋の完成では、こうした努力は無に帰すと思われ、日本政府による無償援助工事の継続や社会発展のために助言活動などを行う必要があると考える。
2025年5月20日 8:35 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
4月例会
令和7年4月20日(日)
日本近現代史研究の観点から考える高度経済成長前期の新潟市政
新潟大学人文学部教授 中村 元氏
<講演要旨>
1950年代から70年代にかけて日本は高度経済成長の時代であった。その前期、50年代の動向について考えてみたい。そしてこの時代の新潟市政をどのように捉えたら良いのか、という視点からお話したい。
戦後の日本経済の回復は速かった。それは国民の勤勉な努力によって培われたが、その成長は「戦後の終わり」をも意味した。しかし近代的大企業の経営と同時に、前近代的小企業及び家族経営による零細企業や農業も存在し、いわば一国に先進国と後進国が併存する二重構造の状態であった。そして日本は世界的な動向を背景に完全雇用の政策も掲げ、50年代はその二重構造と完全雇用の二つの克服をめざした経済成長が大きな課題であった。
50年代鳩山一郎内閣、岸信介内閣により長期の経済計画がたてられたが、その中で国民所得倍増計画も立案されていった。この計画とともに、太平洋ベルト地帯を中心とする既存の主要工業地帯に重点投資する成長路線は、所得格差、地域格差、過大都市の発生等々の諸問題を浮上させた。その結果格差是正の方策や産業立地のあり方などが議論、検討され、地域間の均衡ある発展という方向性がとられるに至った。
51年新潟市は工場誘致奨励条例を制定し、工場の新設や拡充策を打ち出した。47年から59年まで新潟市長であった村田三郎は、新潟市議会で「工場誘致は将来の新潟の資源である」と答弁している。新潟市の工場誘致には有利な条件があった。天然ガスの存在である。新潟の天然ガスは化学工業の主原料として着目され、新潟市が商業都市から工業都市へと大きく転換する重要資源であった。しかし57年頃より新潟市の地盤沈下問題が取り上げられ、その原因の調査や対策事業等で厳しい財政難に直面し、さらに天然ガス採取規制により工場誘致は頓挫せざるをえなかった。
このような中、60年池田勇人内閣により国民所得倍増、過大都市抑制、地方への産業分散対策が発表された。新潟市長渡辺浩太郎はその動きをとらえ、国の公共投資や融資、税制優遇措置を利用する積極的な経済振興構想を表明した。62年国の重要政策として新産業都市建設法が制定された。翌63年新潟地区も新産業都市の指定を受け、64年3月正式決定された。その決定後新たな建設に着手しようとしていた同年6月、新潟地震が発生、新潟市はすべての面で災害復旧に取り組まざるをえなかった。そして経済振興推進の道も中断を余儀なくされた。
以上、50年代から60年代の新潟市政を見てきたが、この時期の新産業都市建設に向けた開発と新潟地震による震災復興とがどう交差したのか、今後の検討課題であると思われる。
2025年4月26日 11:36 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
令和7年3月16日(日)
「神田正平のシベリア抑留記 -父の「我が思い出の記より- 私の昭和戦後史」
講師 当会会員・北方文化博物館館長 神田勝郎氏
〈講演要旨〉
令和4年2月6日玄米を取りに蔵に入り、その時は玄米に向かわず父の書棚に積み上げた書類群に目が行きました。この中に父の書き残した原稿用紙70枚ほどの「我が思い出の記」と10枚程の「あらすじ」がありました。夕食後改めて読み進めると父の戦争体験記であることが分かり、弟妹に連絡して筆者の手で成文化することにした。書棚には『シベリア抑留体験記』の書籍もあり、父も触発され起草したのものと推測した。父の捕虜体験と戦争の悲惨さと残酷さを語り継ぐ史実としてご紹介するものです。
昭和20年1月6日2度目の応召を受ける。横越神社で警防団の出初め式と戦勝祈願祭に出席し激励を受ける。1月8日仙台入隊のため出発、病臥の母は身体に気をつけてと見送ってくれたが、これが母との最期となった。仙台で親戚にお世話になり、博多、朝鮮の羅南に1月30日に着く。中隊の事務室勤務となった。
8月15日の敗戦の報は朝鮮の豊利で知らされる。この連絡を前線の第一中隊成美中尉へ乗馬伝令を命じられ、成美中隊長から「戦争は終わったよ」と言われた。
8月18日豆満江ほとりの日本赤十字社前でソ連の武装解除を受ける。その晩は野宿、月を見てわが家の家族への思いを馳せた。8月21日延吉に入る、その後ハバロフスクに着く。日本兵は2ヶ月間、風呂、水浴は一度もなく、ノミや虱に悩まされ、ソ連も衣服の消毒と入浴を認めた。港に連行されアムール河畔碇泊の黒龍丸が日本人捕虜の宿舎となった。翌日から貨車の石炭降ろしの労働作業が始まり夜12時までかかった。
ある日、船内に「日本新聞」が配られ、広島・長崎の新型爆弾投下、軍艦ミズリー号の降伏調印も知らされた。後にこの教育研修への参加を強制され、ロシア革命からソ連の歩みを辿る思想教育であった。
20年12月31日荷揚げの作業を終え、夕食のパンの支給を楽しみにしていたが、パン焼き器の故障で馬鈴薯の煮物2個というむなしい夕食となり、終生忘れることのできない痛恨の大晦日であった。
21年3月新しい収容所が完成し陸上に移った。ソ連労働者との業務もあり、彼らのカッパライの巧みさを真似して港湾荷役作業で物資を失敬することがうまくなり、メリケン粉・大豆などを小隊に持ち帰って分配した。
同年5月日本人捕虜の身体検査が始まり、軍医の前で四つん這いになりお尻をつままれ、その弾力度で1~3級に分けられた。1・2級は労働、3級はオーカーといわれ労働不可となり、自分は背中のこぶが悪性の腫瘍と見なされ3級となった。そのこぶは帰国後親戚の外科医によって切除手術を受け全快した。21年8月10日弱兵として別の収容所に移され、班長に任命された。弱わった日本兵を帰還させることが自分の使命と考え、朝食前の体操や歌謡曲の合唱、身の上話の開陳、ソ連が提案した「壁新聞」への俳句・短歌・小論などを募った。このころソ連の捕虜対応も緩和、落語など特技の披露や劇団の発表も行われた。
昭和22年3月日本兵捕虜の第一回帰還計画が持ち上がる。5月には背中のこぶにより帰還者に認定された。同年7月6日ナホトカ港から帰還船で出発、7月9日舞鶴沖合で碇泊後、10日入港、京都の東本願寺で一泊、新潟を経て亀田に7月11日着き自宅に帰還した。
父の帰還について、舞鶴入港は舞鶴引揚記念館で、東本願寺での一泊は東本願寺で、また新潟県では「軍籍簿」を閲覧、写し交付で確認することができました。父が生前一言も口にしなかったシベリア抑留記の存在について、新たな畏敬の念を抱かせるものとなりました。
2025年3月20日 7:13 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
令和7年2月16日(日)
近世角田浜村における難船処置の事例
新潟市文書館 高野まりい氏
〈講演要旨〉
新潟市文書館では、代々角田浜村の庄屋を務めた大越家に伝わった3200点ほどの文書を整理している。この資料の中から江戸時代に角田浜村の海岸に漂着した難船の事例から、難船救助や船道具、積荷の処理がどのように行われたのか報告する。
角田浜村は、村明細帳に「当村男女稼耕作并海猟仕申候」とあり半農半漁とされる。大越家には浦高札があり、海難救助を担う浦村であった。文書の中に船往来があり村に廻船もあったかと思われるが詳細は不明である。安政5(1858)年の絵図によれば、角田浜村の海岸は遠浅の砂浜で、沖には岸に平行して三列の砂瀬が並んでおり、大型の廻船が入る湊ではなかった。
難船の事例を8例あげる。事例1は、享保13(1728)年に破船が漂着した。村は船材や道具を引揚げて番人をつけて保管した。船は佐渡松ケ崎の船で、寺泊に漂着した乗組員や新潟・寺泊の船宿が確認に来た。引揚げた船材の不足を問題にしたが、翌年、引揚物を受け取っている。
事例2は、元文3(1738)年の東岩瀬の廻船が難風で積荷を捨て角田浜に漂着した。村人が乗組員を救助し、船も引揚げ、出港地新潟の船宿に引渡した。
事例3は、佐渡加茂郡の漁船が元文4年に角田浜に漂着し、村人大勢で乗組員と漁船を救助した。
事例4は、文政3(1820)年に酒田を出港した丹後の廻船が村の沖合で破船した。村役人が村人を率いて海中から積荷と船道具を引揚げた。積んであった荷物と引揚げた荷物を照合したうえで、引揚品は船頭・新潟船宿に引渡された。
事例5は、文政5年に佐渡杉野浦村の破船が漂着した。佐渡から船主が来村し自己の船と確認をして船道具類を引取った。
事例6は、寺泊の7人乗りの漁船が角田浜沖で破船した。村人が救助したが1人が溺死した。
事例7は、文政11年に新潟湊の廻船が塩屋で破船し、船道具が漂着した。引揚げた船道具は船主・新潟町問屋へ確認の上引渡されたが、船道具代の十分一として金1両余が村へ払われた。
事例8は、弘化4(1847)年に佐渡水津を出港した新潟町の廻船が角田浜沖で破船した。村では粉々になった船道具や積荷を引揚げた。新潟の船主・船頭が確認して引き揚げ品を受取り、そのうえで角田浜村において売払っている。
以上の事例から、浦村である角田浜村では難船があった場合には村役人主導のもとで人命救助や積荷・船道具を引揚げ、また破船の船道具が漂着した場合にも引揚げて、村が保管した。これらの品々は船頭・船主・船宿らと村役人が立会って確認し、引渡し、請取りがなされた。その後、これらの品々が村で売り払われた事例もあった。
大越家文書は整理中であり、今後の調査によって多くのことが明らかになると思われる。
2025年2月22日 9:49 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
1月例会
令和7年1月18日(土)
新潟から出る遊女、新潟へ来る遊女
新潟大学人文学部教授 原 直史氏
<講演要旨>
はじめに遊女「かしく」の半生を紹介する。嘉永4年(1851)蒲原郡東汰上村(新潟市西蒲区)に生まれ、安政5年(1858)7歳で下野国合戦場宿(栃木市)福田屋に召し抱えられ遊女となった。慶応2年(1866)15歳で江戸深川はしや政五郎方へ遊女として召し抱えられ、明治4年(1871)に新吉原三州屋に売り渡された。翌年「遊娼妓解放令」が出されると、なじみの吉原海老屋召使竹次郎と夫婦の約束を交わした。しかし政五郎が債権を主張し新吉原に売ると訴えたため、「かしく」らは「遊女はいやだ」と役所に訴え出る。江戸時代の経世家佐藤信淵は、「越後は間引を行わないが、女子を他国に売り出している。北越の売婦を非難する者もあるが、間引に比べれば仁術ともいえる」と述べている。
蒲原郡から他国への飯盛奉公は多い。文政5年(1822)武州粕壁宿(埼玉県春日部市)違法営業で検挙された飯盛女21人中18人が越後出身、うち15人が蒲原郡出身。文久2年(1862)野州雀宮宿(栃木県宇都宮市)の下女53人のうち43人が越後出身(うち36人が蒲原郡)。文政6~7年頃の奥州郡山宿(福島県郡山市)で飯盛女・子供とみなされる167人のうち9割超の154人が蒲原郡出身。単に「真宗地帯」だけでは解けない。
移動する新潟遊女について。新発田城下町は公娼を置かず、私娼「かぼちゃ」で著名。新発田町に文久2年(1862)10月、新潟売女を連れ寄せていた城下町人が複数摘発・処罰された。同時期に新発田川を航行する新興集団「通船路船乗」が形成され、元治元年~2年(1864~65)には木崎河岸の茶屋集団との紛争が起こるが、文久2年の規制強化により、遊興の場が新発田より陸路三里で到達でき新潟売女を呼び寄せられる木崎に移行していく。そもそも新潟の遊女は本来古町通・寺町通を営業範囲として、長岡領時代より「他門・本町通、芸者・遊女横行御停止」がたびたび触れられていた。新発田や木崎まで出かけたのは公認の遊女だろうか、あるいは後家などの私娼であろうか。天保8年(1837)会津屋金太抱女よしが客人に拘束され髪飾りを奪われる一件があったが、この客人は上州無宿であり、関東への奉公人を抱えに来ていた。この時期、揚屋公認の遊女を巡って様々な事件が起こっており、上州無宿をはじめとした広い交流のなかに遊女たちの境涯がある。
次に野州合戦場宿への奉公について。嘉永7年(1854)新潟本町通借家娘もと22歳が合戦場宿旅籠屋に奉公し、請判を同宿の定右衛門に依頼している。合戦場宿には毎月の抱女数に応じた刎銭を出し、宿内入用の一部を賄い、宿役を勤める住人に残額を割渡すシステムがあり、そのために飯盛旅籠屋はある種の仲間を結成している。定右衛門は旅籠屋ネットワークに通じた女衒的存在である。こうしたネットワークの形成こそが蒲原郡から大量の飯盛女を送り出していったと想定できる。そうしたネットワークはいつ頃どのようにできていくかが大きな課題である。
2025年1月21日 7:05 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
11月例会
令和6年11月17日(日)
演題:「疑惑の海峡 北前船海死事件を追う」
講師:当会理事 横木 剛 氏
<講演要旨>
新潟町の廻船問屋前田松太郎(元は当銀屋重松と名乗る)は、北前船稼業で築き上げた資金を元手に、安政6(1859)年に廻船問屋株(営業権)を取得した。その時期の客船帳の中に、荒浜牧口庄三郎、その代理人米平がやって来て、そこで囲い船されていた小川屋喜兵衛の中古廻船を安政5年に買い入れ、整備して翌年2月に12人乗りの船「興栄丸」として出帆したとの記録が残されている。
この牧口庄三郎は文化元(1804)年生まれ。牧口家三代目当主で、天保年間に五百石程の中型船を複数所有し、蝦夷地から上方までの買積廻船業を展開し、米や荒浜近在の麻の鰊網を蝦夷地へ、塩引き鮭や魚肥、昆布などを上方へという交易を行なっていた。
現在柏崎市立図書館に所蔵されている「牧口庄三郎家旧蔵文書」の中に、この牧口庄三郎が訴訟人となって、万延元(1860)年7月に、居所を管轄する領主役所(与板藩奉行所)に村庄屋、割元を経由して、ある事件の吟味と裁判開始を訴えたことが分かる願書の控えが残されている。
その訴訟相手は、雇用していた水主11人であり、前々年に購入したばかりの「興栄丸」が、根室から帰還途中に尻岸内村沖で難船して、船頭米平のみが不審死し、積荷処理も正当に行われていないという疑念から訴え出たものであった。
「興栄丸」は安政7年春に蝦夷地へ向け出帆し、箱館→酒田→箱館と回り、冬季間は箱館で浮き囲いしていた。翌年3月15日に根室に向かい、根室から戻る途中の5月11日尻岸内村沖で事故に遭った。村役人を通じて急遽箱館まで飛脚を差立て、船宿浜田屋の手代鉄蔵と小宿由松の仲介で箱館奉行所へ出役を願い出て、米平の死体と積荷を処理した。
水主たちは、その後箱館にやって来た庄三郎の息子虎之助とともに帰国し、さらに取り調べられることになり、8月には牧口に対して、状況を詳らかした詫び状と金銭的損失に対する念書を差し出すこととなった。
その後牧口は、水主たちとの訴訟がある程度まとまった後の11月に、箱館奉行所と尻岸内村へ文書を出している。積荷を売り払うことに加担した(もしくは横領を主導した可能性もある)箱館の廻船問屋と、顛末を隠すことに協力し金品を得た尻岸内村を追及する方向に向かっているが、以後の関連史料は見当たらず、結末は不明である。今回の事件については、本来船の指導役である船頭の、米平のみがどうして死亡したのかの疑惑や、諸帳面の紛失により横領の疑念もぬぐい切れない。あわせて水主たちの金銭欲求や雇用管理の関りで、買積廻船経営における水主の労働条件や環境という課題も提起され、北前船経営は、廻船主にとって管理が困難なビジネスという一面が見えてくる。
2024年11月23日 4:39 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
10月例会
令和6年10月20日(日)
演題:新潟開港と戊辰戦争-新潟奉行代理田中廉太郎光儀(れんたろうみつよし)の生涯と御料所新潟の終焉-
講師:東京大学史料編纂所学術支援専門職員 杉山 巖 氏
〈講演要旨〉
本日は新潟開港と幕末、明治維新期の新潟の歴史について、新潟奉行代理であった田中廉太郎光儀の生涯と関連させてお話したい。
新潟の開港が最終的に決まったのは慶応3(1867)年8である。その開港をひかえ外国方の上級事務を担当していた白石千別、糟屋義明が新潟奉行に就任した。また同4年正月、田中光儀が新潟奉行所ナンバー2の組頭として就任し、さらに同年閏4月新潟奉行勤向(奉行代理)に昇任した。
田中光儀は幕府代官所手代の子息として生まれ、のち浦賀奉行所の役人であった田中家の養嗣子となり家督を相続した人物である。彼は浦賀奉行所や長崎奉行所に在勤し、その後幕府の外国方の役人となり小笠原島問題を担当することとなった。この時小笠原島開拓担当の外国奉行組頭が白石千別で、その下の調役が田中であった。
また彼は横浜鎖港問題の交渉使節団の一員としてヨーロッパへ派遣された。使節団は文久4(1864)年正月上海に到着、その後各地を経由しパリに到着、フランスと交渉するが失敗、同年7月帰国。団員は失敗の咎を受け、田中も役職を離任した。
慶応3年10月14日に大政奉還が行われ、同年11月徳川家は新潟に在勤していた新潟奉行白石千別を江戸に呼び戻した。新潟開港が切迫していたため白石は江戸在勤の糟屋義明らと協議し、同3年12月7日の開港予定を翌4年3月9日に延期することを決定した。そして同4年正月新潟奉行所組頭に田中が就任し、白石、田中の二人は新潟に来た。二人は外国奉行所時代の上司と部下であった。
同4年3月15日明治新政府の北陸道鎮撫使が来越、新潟奉行も召喚された。鎮撫使にようやく会えた田中は行政事務の引き継ぎを命じられた。そして4月4日徳川家の指示を仰ぐため白石と田中は会津を経由して江戸へ行った。白石は新潟奉行を免じられ江戸にとどまることとなった。一方田中は奉行勤向に就任し5月2日新潟に戻った。戻った彼は新潟を米沢藩の「当分預所」とする決断を下した。この決断は徳川家の方針にそったもので田中が勝手にやったわけではないと言える。田中の行動はあくまでも徳川家の家来としての行動であった。そして6月2日田中は江戸に向かって新潟を出立した。
明治時代田中は豊岡県(現兵庫県)の県令に就任し、その一方で大木喬任や井上馨の顧問のような仕事もした。また木戸孝允との交流もあり新政府要人らに提言したりした。今その活動を物語る手紙などが残されている。
2024年10月29日 7:56 PM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
9月例会
令和6年9月15日(日)
演題:菖蒲塚古墳と菖蒲御前伝説
講師:新潟市歴史博物館副館長 小林隆幸 氏
〈講演要旨〉
菖蒲塚古墳は県内最大の前方後円墳で、4世紀に蒲原平野に君臨した有力者の墓です。古墳はやがて放置されますが、その異様性・神秘性から信仰の対象ともなり、古墳名称の由来となる菖蒲御前伝説との結びつきもあり、今日に至る人々との関係を概観してみます。
菖蒲塚古墳は4世紀半ば頃造られた全長53mの前方後円墳、金仙寺裏山の墓地の中に所在。副葬品には鼉龍鏡(径23.7㎝)・ヒスイ製勾玉や管玉があった。陪塚は隼人塚古墳。菖蒲塚古墳は大王墓の渋谷向山古墳(景行天皇陵)の5分の1で同企画。近接する南赤坂遺跡には北方系文化の系譜をもつ続縄文土器や土器も見つかり、菖蒲塚古墳の主のもとで北方の人々との鉄器の素材や皮などとの交易が行われていた可能性がある。
中世に入ると末法思想を背景に古墳が経塚として利用され、神聖な場所に位置づけられる。菖蒲塚古墳には、嘉応2(1170)年銘と享禄3(1530)年銘の経塚が出土している。嘉応2年銘は金仙寺が江戸期に発掘したもの、宋代の青白磁の小壷と合子、和鏡5点、陶製壺2点を埋納。享禄3年銘は六十六部聖が全国を巡礼し法華経一部を納めたもので越後では霊場として菖蒲塚が選定されたものと思われる。
菖蒲塚はその名称となった菖蒲御前の墓と伝えられている。金仙寺の山号は菖蒲山である。菖蒲御前は治承4(1180)年に宇治で戦死した源頼政の妻で、夫戦死した後に越後に逃れた。その子が後に小国氏の支城であった天神山城主となった。この菖蒲御前と関連するのが、金仙寺所蔵の聖観音坐像の底板に元徳3(1331)年「大施主貞阿」「女大施主」とある。また菖蒲塚古墳の近辺から掘り出された石塔に「菖蒲貞阿禅尼」印刻されている。過去帳には「菖蒲貞阿禅尼」が貞応2(1223)年没とあり、印刻名と同一人物と思われる。金仙寺で発掘された装身具も高貴な女性を連想させ、菖蒲御前伝説を後押しした可能性もある。
また古墳は盗掘され、鏡(鼉龍鏡)などが出土したとされ、盗掘品は市場に出ている。金仙寺の発掘の時期は文政期と思われるが、新発田藩の丹羽伯弘は鏡を実見し天保15年に拓本を取っており、この拓本は近年みなとぴあに寄贈されている。盗掘された鏡はしばらく最初の所有者が保管、昭和27年齋藤秀平が漢式の四神四獣鏡と判定し話題となった。同年上原甲子郎氏が東京国立博物館に持ち込まれていた鏡の拓本を取った。以降、鏡は所有者の手を離れ行方不明となり昭和36年に所在が分かり、上原甲子郎氏が購入、令和2年に東京国立博物館に寄贈された。昭和37年に鏡は新潟県指定文化財、金仙寺所蔵の経塚出土品(重要文化財)はみなとぴあで保管・管理、地域の重要な文化資源となっている。
菖蒲塚古墳は地域の首長の墓として造営、中世には神聖な場所として経塚の役目をもち、近世には伝説と結びついて信仰の対象となっている。古墳時代の遺跡だけではなく、各時代に役目をもった複合遺跡といえるのではないか。
2024年9月18日 11:58 AM |
カテゴリー:月例会 |
コメント(0)
« 古い記事