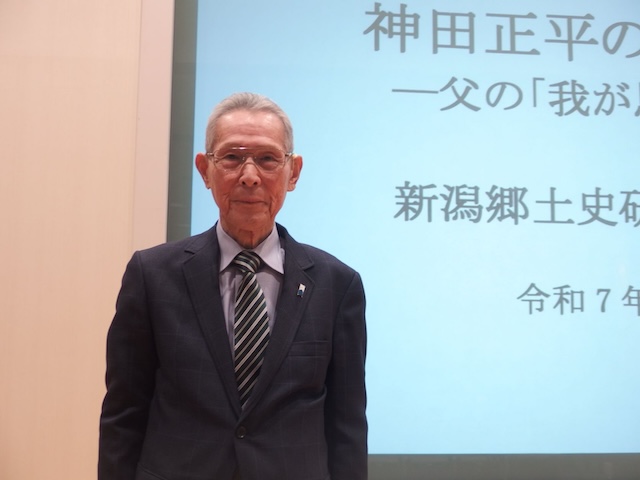3月の例会=報告
令和7年3月16日(日)
「神田正平のシベリア抑留記 -父の「我が思い出の記より- 私の昭和戦後史」
講師 当会会員・北方文化博物館館長 神田勝郎氏
〈講演要旨〉
令和4年2月6日玄米を取りに蔵に入り、その時は玄米に向かわず父の書棚に積み上げた書類群に目が行きました。この中に父の書き残した原稿用紙70枚ほどの「我が思い出の記」と10枚程の「あらすじ」がありました。夕食後改めて読み進めると父の戦争体験記であることが分かり、弟妹に連絡して筆者の手で成文化することにした。書棚には『シベリア抑留体験記』の書籍もあり、父も触発され起草したのものと推測した。父の捕虜体験と戦争の悲惨さと残酷さを語り継ぐ史実としてご紹介するものです。
昭和20年1月6日2度目の応召を受ける。横越神社で警防団の出初め式と戦勝祈願祭に出席し激励を受ける。1月8日仙台入隊のため出発、病臥の母は身体に気をつけてと見送ってくれたが、これが母との最期となった。仙台で親戚にお世話になり、博多、朝鮮の羅南に1月30日に着く。中隊の事務室勤務となった。
8月15日の敗戦の報は朝鮮の豊利で知らされる。この連絡を前線の第一中隊成美中尉へ乗馬伝令を命じられ、成美中隊長から「戦争は終わったよ」と言われた。
8月18日豆満江ほとりの日本赤十字社前でソ連の武装解除を受ける。その晩は野宿、月を見てわが家の家族への思いを馳せた。8月21日延吉に入る、その後ハバロフスクに着く。日本兵は2ヶ月間、風呂、水浴は一度もなく、ノミや虱に悩まされ、ソ連も衣服の消毒と入浴を認めた。港に連行されアムール河畔碇泊の黒龍丸が日本人捕虜の宿舎となった。翌日から貨車の石炭降ろしの労働作業が始まり夜12時までかかった。
ある日、船内に「日本新聞」が配られ、広島・長崎の新型爆弾投下、軍艦ミズリー号の降伏調印も知らされた。後にこの教育研修への参加を強制され、ロシア革命からソ連の歩みを辿る思想教育であった。
20年12月31日荷揚げの作業を終え、夕食のパンの支給を楽しみにしていたが、パン焼き器の故障で馬鈴薯の煮物2個というむなしい夕食となり、終生忘れることのできない痛恨の大晦日であった。
21年3月新しい収容所が完成し陸上に移った。ソ連労働者との業務もあり、彼らのカッパライの巧みさを真似して港湾荷役作業で物資を失敬することがうまくなり、メリケン粉・大豆などを小隊に持ち帰って分配した。
同年5月日本人捕虜の身体検査が始まり、軍医の前で四つん這いになりお尻をつままれ、その弾力度で1~3級に分けられた。1・2級は労働、3級はオーカーといわれ労働不可となり、自分は背中のこぶが悪性の腫瘍と見なされ3級となった。そのこぶは帰国後親戚の外科医によって切除手術を受け全快した。21年8月10日弱兵として別の収容所に移され、班長に任命された。弱わった日本兵を帰還させることが自分の使命と考え、朝食前の体操や歌謡曲の合唱、身の上話の開陳、ソ連が提案した「壁新聞」への俳句・短歌・小論などを募った。このころソ連の捕虜対応も緩和、落語など特技の披露や劇団の発表も行われた。
昭和22年3月日本兵捕虜の第一回帰還計画が持ち上がる。5月には背中のこぶにより帰還者に認定された。同年7月6日ナホトカ港から帰還船で出発、7月9日舞鶴沖合で碇泊後、10日入港、京都の東本願寺で一泊、新潟を経て亀田に7月11日着き自宅に帰還した。
父の帰還について、舞鶴入港は舞鶴引揚記念館で、東本願寺での一泊は東本願寺で、また新潟県では「軍籍簿」を閲覧、写し交付で確認することができました。父が生前一言も口にしなかったシベリア抑留記の存在について、新たな畏敬の念を抱かせるものとなりました。